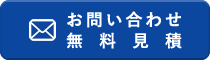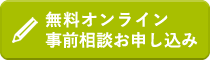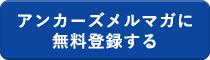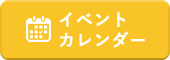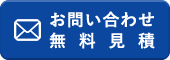- ホーム
- 毎日ブログ
毎日ブログ
622/1000 ストーブの静かな第二章
2025/07/31
昨シーズン、薪ストーブを新しくした。
燃費や暖房効率を考えて、ヨーロッパ製のものに入れ替えた。
最近のストーブは本当に優秀で、少ない薪でもしっかり部屋を暖めてくれる。
長年使ってきた旧ストーブは、アメリカ製の無骨だけど頼れる存在だった。
特に使い道も無く、放置されていてそろそろお役御免か…と思いながらも、すぐに処分する気にはなれなかった。
この夏、その旧ストーブはレコードプレーヤーとスピーカーの台として静かに活躍している。
どっしりと重く、安定感は抜群。
音響機器を置くにはちょうどいい高さと広さ。
何より、その存在感が音のある暮らしによく似合う。
火は入っていないけれど、音をのせ、灯りを添えると、不思議とあたたかみが戻ってくる。
レコードの針が落ちる瞬間、まるでまたストーブが呼吸をしているようにも見える。
いつかまた、あの中に薪をくべる日が来るかもしれない。
でもそれまでは、音とともにあるこの日々を、もう少しだけ楽しんでみようと思っている。620/1000 自分の都合じゃなく、相手の未来を語ろう。
2025/07/29
昨日、出羽商工会さん主催の人材採用セミナーに参加しました。
テーマは「お金をかけずに思い通りの人材採用を実現」。
内容は驚くほど今の私たちにフィットしていて、「そうすればいいんだ!」という気づきの連続でした。
特に印象に残ったのが、講師の方が語った「マッチ売りの少女」の例え。
「このマッチが売れないと、お父さんに叱られるんです。お願いします!買ってください!」
この少女の姿は切なく心を打ちますが、同時に、誰もマッチを買ってはくれません。
なぜか。それは彼女の言葉が“自分の都合”ばかりだからです。
買い手の気持ちではなく、売り手の事情が前面に出てしまっているから。
この話を聞いて、思わずハッとしました。
求人でも同じことをしていなかっただろうか、と。
「人が足りない」「来てくれないと困る」「助けてください」
求人原稿に、そんな“自社の都合”だけを並べてはいなかったか。
相手の立場に立たないまま、一方的な“お願い”だけをしてはいなかったか。
講師の言葉は続きます。
「求人は広告じゃない。ラブレターなんです」
誰に、何を伝えたいのか。どんな人と働きたいのか。
その人の心に届く言葉で、自分たちの“想い”を伝えること。
そこに共感が生まれ、初めて人が集まってくる。
求職者の心に届く求人。
それは、ただ人を“集める”のではなく、
“惹きつける”ことで、未来を共につくる仲間を迎えること。
セミナーを通して、求人の本質を改めて学びました。
マッチ売りの少女にならないように。
まずは、自社の求人ページを、自分たちの言葉で見直してみます。
“火を売る”のではなく、“温もりを届ける”ために。
618/1000 温度でわかる、山形の人情
2025/07/27
「おにぎり、温めますか?」
山形のコンビニでは、これが当たり前の会話だ。レジで聞かれると、つい「お願いします」と答える。寒い季節ならなおさら。あったかいおにぎりを片手に車に戻ると、なんだか少し報われたような気がする。
でもこのやりとり、県外ではほとんどないのだそうだ(夕食の時に家族が話していた)。
同じように、山形のガソリンスタンドでは「室内清掃用のタオル」が出てくることがある。しかも冬はほんのり温かい。これもまた、ありがたい気配り。
そして、暑い今の季節には「冷やす文化」が登場する。冷やしラーメン、冷やしシャンプー。とことん冷やす。容赦なく冷やす。でも、それは決して冷たいのではなく、「相手が求めていること」をちゃんと分かっているから。
そう。温めるも、冷やすも、その根っこにあるのは思いやりなんだ。
だからかもしれない。山形には、創業百年を超える老舗が多い。商売を続ける上でいちばん大事なのは、技術でも資本でもなく、人への気配りだ。変わるものに合わせて、変わらない心を持ち続ける。それが、山形の空気には確かにある。
たったひと言の「温めますか?」
そっと差し出されたタオル
氷で冷えた一杯の冷やしラーメン
それらはみんな、温度の話じゃない。
心の温度を感じる風景なんだと思う。
616/1000 ギラギラじゃない、キラキラがある場所
2025/07/25
昨日は、山形市中央倫理法人会のモーニングセミナーで講話をさせていただきました。
テーマは「倫理法人会が楽しくなるには?」という、ちょっと素直で、ちょっと深い問いかけ。
実は私、倫理法人会に入って今年で20年になります。
この20年の間に、何度思ったかわかりません
「こんな会、なければどんなにか楽なのに」って。
朝は早いし、役は回ってくるし、忙しい時ほど予定がかぶる。
眠い目をこすって会場に向かう朝、
“なんで自分だけ…”と心の中でぼやいた日もありました。
でも、辞めずに続けてきたのは、
この会に「自分を育ててくれる何か」があったからです。
もしこの会に入っていなければ、
きっと出会っていなかった人たちがいます。
聞くことのなかった価値観があり、
行くこともなかった地域がありました。
そして何より、
ここにはロールモデルとなる素敵な人たちがたくさんいます。
ギラギラとした成功者ではなく、
人生の厚みを感じさせる、キラキラとした人たち。
そういう人たちに出会うたびに、
「自分も、あんなふうに、かっこよくなりたいな」って思うんです。
昨日の講話では、私自身が会を通じて変わってきたこと、
そして「楽しさは自分の関わり方で決まる」ということをお話しました。
特に共感をいただいたのが、
「やらされ感」から「やりたいこと」へ、という視点。
MS委員や朝礼リーダー、会報係など、
一見面倒に思える役割も、
自分なりに工夫して取り組めば、それはもう“自己成長の場”です。
そして、
「ただ知ってる人」より「語り合える仲間」ができること。
講話を聞いて終わるのではなく、自分ごととして動き出すこと。
学びを受け取るだけでなく、誰かに届けていくこと。
そういう積み重ねの中で、私はこの会に育てられてきたんだと思います。
倫理法人会は、単なる勉強会でも、名刺交換の場でもありません。
“人として耕される場所”。
“心がキラリと光る場所”。
そして、気づけば自分もその光の一部になっている
そんな会だと、私は思っています。
山形市中央倫理法人会の皆さま、
昨日は本当にあたたかく迎えていただき、ありがとうございました。
614/1000 運気のはじまりは、ポロリと
2025/07/23
今日、奥歯の銀歯がポロリと取れた。
「え、また?」と自分でも思うくらい、ちょいちょい外れる。もう何度目か分からないけれど、私にとってはこれ、ちょっとした吉兆だと思っている。
痛みはない。焦りもない。むしろ、「ああ、そろそろ何か動くな」という合図のように感じているのだ。いわば“付きものが取れた”感覚に近い。
銀歯というのは、見た目にも機能的にも、長く口の中に居座る「異物」だ。もちろん、お世話になった歯医者さんに失礼な言い方かもしれないけれど、身体が「もうこれ、いらないよ」と言っているような気がしてならない。
そういえば、これまで銀歯が取れたあとには、不思議と身の回りが軽くなる。人間関係がスッと整理されたり、考え込んでいたことが急にどうでもよくなったり、何かに執着していた自分がふっと緩んだり。
今回はどんな「何か」が取れたのだろう。
昔は、こういう出来事をただの「アクシデント」として扱っていた。でも最近は、ちょっと立ち止まって意味づけをしてみるのが楽しい。根拠はない。でも、根拠がないからこそ、自由だ。
とりあえず、銀歯はポーチに入れておいた。週末に歯医者さんに行くとして、それまでのあいだ、少し気をつけながら、でもちょっとワクワクしながら日々を過ごしてみようと思う。
612/1000 気候変動とツバメの産卵回数
2025/07/21
毎年のことだけど、会社のテラスにツバメが巣を作った。今シーズン2回目。
2回目はなぜか網戸に巣を作ろうとしていたので、この巣はやむを得ず撤去。
模様を伺うも狙い通り、彼らは1回目とまったく同じ場所に巣作りを始めた。
無事に産卵したものの、しばらく動きがなくて心配していたが、先日ようやくヒナが孵った。
そして成長のスピードがとにかく早い。
先週ようやく巣のフチからくちばしがのぞいたと思ったら、
今日はもう親鳥と見分けがつかないほど立派に育っている。
5羽のヒナたちは、そろそろ巣立ちの時を迎えそうだ。
ここまで来ると、ちょっと気になってくるのが「3回目って、あるのか?」ということ。
これまでは毎年2回で終わっていた。
でも、こうして気温が高く、夏が長くようになってくると、
西日本のように3回目の繁殖もあり得るのではと、ちょっと思ってしまう。
実はこの“3回目問題”、我々にとっては結構現実的で、ツバメの子育てが終われば糞で汚れたテラスの大掃除と、張っていた養生シートの撤去が待っている。
もしも3回目があるのなら、今すべて片付けるのは早い。
とりあえずライトな清掃にとどめて、様子見しようかと悩み中。
こうしたツバメの繁殖回数も、気候変動のバロメーターになるのではないかと考えている。
さて、3回目があるのかどうか。大げさだけど2025年という年がそれ以前と以後になるのかもしれない。
まずはこの5羽が無事に巣立ってくれることを願いながら、しばらくは上を見上げる日々が続きそうだ。610/1000 梅雨明けとともに、海がひらく
2025/07/19
昨日、地元の海水浴場が海開きを迎えた。
同じ日に梅雨明けが発表されるのは、実はとても珍しいことだ。
例年であれば、曇り空のもとでの“どんよりした”海開きが定番。
けれど今年は朝から晴天、まるで夏がそのまま押し寄せてきたようだった。
とはいえ、夏の日差しが強ければ強いほど、
海岸に人が集まるかというと、そう単純でもない。
炎天下すぎると、逆に人足は遠のく。
自然相手の商売やイベントは、そのさじ加減が難しい。
昨年の今ごろは、そんな気候の“極端”さを実感させられた。
梅雨明け前の豪雨により、地域は大きな被害を受け、私たちも現場対応に追われた。
だからこそ、今年は備えを見直した。
豪雨災害への対応マニュアルを一から整え直し、
昨日のミーティングで社員全員に共有したところだ。
夏は楽しい季節であると同時に、備えの季節でもある。
すべてが“何も起きなかったね”で終わることを願いつつ、
そのための準備を、今年もひとつずつ積み重ねていく。593/1000 家財整理の見積もりは誰のためにしているのか
2025/07/17
家財整理の見積もりをしていると、ふと考えることがある。
「私は、いったい誰に向けてこの見積もりをしているのだろう?」
形式的な依頼者はたいてい、不動産屋さんや相続人の方々だ。
もちろん彼らは必要があって連絡してくれるのだけれど、どこか“他人事”の空気をまとっていることが多い。
「とにかく早く片づけてほしい」
「中のものは全部処分でいいです」
そんなふうに、事務的に淡々と話が進んでいく。
でも、家の中に一歩足を踏み入れると、空気が変わる。
暮らしていた人の気配が、そこかしこに残っている。
台所には使い込まれた鍋、壁には色あせたカレンダー、タンスにはまだ折り目のついた服。
誰かの生活の記憶が、静かにそこに息づいている。
そう気づくと、私たちは本当の依頼者は目の前にいる人ではなく、
“この家で長年暮らしてきた、もういない誰か”なのだと思い至る。
だから、たとえ「全部処分で大丈夫」と言われても、
私たちはその言葉を鵜呑みにせず、引き出しの奥や押し入れの中に、
まだ何か大切なものが残っていないか、静かに目を凝らす。
そして、たとえその見積もりが最終的に仕事に結びつかなかったとしても、
私たちはこの家と、その暮らしに、正直に向き合いたいと思う。
事務的な依頼者にモヤモヤしながらも、
心の奥では、本当の依頼者に向き合っているつもりで。
591/1000 旅行に行くにカバンは小さい方がいい
2025/07/15
現場に出てクタクタになった日。
それでも最後の掃除機がけが、実はけっこう好きだ。
家財整理の仕事って、体力仕事でもある。
運んで、分けて、拭いて、また運んで。
一軒終わると、皆そろって「腰いてぇ〜」と呻いている。
……のだが、私は違う。
なぜか、腰痛が来ない。
20年やってきて、それなりに無理もしてきたはずなのに、
腰に来たと感じても次の日には回復している。
現場スタッフは皆、腰ベルトや湿布、時にはストレッチ体操までやっている。
でも私はといえば、汗だくになっても、大丈夫。
典型的な骨格ウエーブの体型がきっと柳のようにいなすのだろう。そう自分では感じている。
だから「やっぱり神様に選ばれてるんじゃないか」と、
本気で思っている節がある。
それで、空っぽになった家で(静かに?)掃除機をかける時間は、
本当に気持ちがいい。
何にも無くなって、風が通る部屋。
床に光が差し込み、お客様の笑顔が浮かぶ。
モノがなくなると、人の顔が柔らかくなる。
人生の満足度って、持ち物の量と反比例するって私は信じている。
旅行に行くのにカバンは小さい方がいい。人生もまた。
589/1000 こだわりを、もう一度
2025/07/13
今日は、築15年になる我が家のメンテナンスをせっせとこなしていました。
かつて、建築当時にこだわりにこだわって作ってもらった造作キッチン。タイル貼りのカウンターが自慢だったのですが、最近どうも水漏れが…。「やるしかないか」と、防水コーキング材を片手に、素人なりの応急処置を。
照明も同じく、当時選び抜いたシャンデリア風のブラケットライトが、金属部分に錆が出たり、ガラスがくすんだり。こちらはメラミンスポンジでゴシゴシ。気持ちのいいくらい輝きを取り戻しました。
思えば、家を建てる前は、雑誌を何冊も読み漁って、細部まで設計士さんと相談しながら「私らしい家」を夢見ていたはずなのに。
建てたとたん、現れたのは現実。子育てに追われ、気づけば効率重視。オシャレとかデザインとか、封印したままの日々が続いていました。
でも最近、少しずつ風向きが変わってきました。子どもたちもあと数年もすれば巣立っていく予定。そう思うと、なんだか急に家が「私の場所」としてよみがえってきた気がします。
せっかくこだわって建てた家。くたびれてきたところは手を入れながら、当時のデザインや素材の良さをもう一度見つめ直していきたい。
これからは「使いやすさだけじゃない、心地よさも大事にしたい」と思えるようになった今だからこそ、また少しずつ“家づくり”を楽しめる気がしています。
差し当たって、まずはレコードプレーヤーを置ける部屋を仕立ててみようかなと。
音のある空間、好きなものに囲まれた空間。そんな時間を自分にプレゼントするのも悪くない。
15年目の我が家、まだまだ進化の途中。
これからは、過去の自分が選んだものに感謝しつつ、今の私の“好き”を少しずつ取り入れていく計画です。587/1000 連絡がないという知らせ
2025/07/11
今日は空気がカラッとして、風が強く、まるで高原にいるような一日だった。
事務所の前の空き地に広がる草むらが、そよそよと風に揺れている。
その様子を眺めていたら、なんだか時間の流れがゆっくりになったような気がした。
東京では昨日、大雨で河川が氾濫した地域もあったらしく、事務員さんと「うちの子たちは大丈夫だったかな」と自然と話題に上る。
こちらはこんなにも穏やかなのに、同じ日本でこうも違うものかと、不思議な気持ちになる。
「親は子どものことを常に考えているが、子どもが親を思うのはたまにらしい」
以前どこかで読んだそんな言葉を、ふと思い出す。
地震が起きたらどうするか、避難場所はどこか。
連絡手段は一応伝えてあるけれど、いざという時に本当に機能するのだろうか。
もし海外転勤になったら、あの子はちゃんとやっていけるのか。
気にしたところでどうなるわけでもないけれど、親というのはいつも、そんなことばかり考えてしまうものらしい。
とはいえ、今のところ特に連絡はない。
それが、何よりの知らせなのだと思う。
585/1000 放題の違和感と、食べものの未来
2025/07/09
環境省の調べによれば、2022年、日本で発生した食品ロスの量は約472万トン。
1日あたりに換算すると、およそ東京ドーム1杯分にも相当するという。
しかもその約半分が、家庭から出ているというのだから驚きだ。
そんな中、先日参加したビアパーティーで、ふと気づいたことがあった。
いわゆる「食べ放題・飲み放題」形式。
幹事としてはありがたい料金体系だが、
今回は少し様子が違っていた。
料理の補充が、以前より控えめ。
ラストオーダーも早めに切り上げられ、
全体的に「食べ残しを減らす」工夫が感じられた。
これはきっと、フードロス対策なのだろう。
けれど、その一方で、
「食べなきゃ損!」「元を取らなきゃ!」という空気も、
どこかエンタメとして根強く存在している。
子どもには「好き嫌いしない」「いただきますの心を大切に」と教えていながら、
大人たちがその隣で、無理にお腹に詰め込んでいたら、
いったい何が“食育”なのかと考えてしまう。
放題という形式自体が悪いわけではない。
けれど、その楽しみ方に、
ちょっとした“節度”や“意識”があるだけで、
ずいぶん違う未来になるのではないか。
だいいち、食べすぎて健康を害したら、
「元」どころか「損」しているのでは? と思う。
食べ物には、たくさんの手間と時間と命が込められている。
本当に美味しいものは、
たくさん食べることではなく、
ちゃんと味わうことで、心に残っていく。
日々ごみを扱う私たちも、やはり心と胃袋という機関によって命を繋いで頂きたいと願ってやまない。
食べものと、もう少し、丁寧につきあっていきたい。583/1000 なんか違う、から始まる一着
2025/07/07
スーツを仕立てるというのは、実に難しい。
無限とも思えるパターン、ちっちゃな生地サンプル、
そして、鏡の前で「これ、似合うんだろうか?」と自問自答する日々。
正直、あのサンプル生地だけで全体像を想像するのは無理な話しだ。
ついWEBで誰かの着こなしを参考にしてみるものの、
その誰かは当然ながら自分と違う。
似合うかどうか? わからない。
そう、これはもう、経験と失敗が物を言う世界かもしれない。
そんなこんなで
やっと完成した今回の一着だったが、
やはり気になって、仕立て直しを決意する。
違和感はごまかせない。
訪れたのは近所の仕立て直し店。
店先には、80代?ぐらいに見える小柄な女性が座っていた。
一瞬、「大丈夫かな…」とよぎる不安。
だが、その方が放った第一声が、
「LINE登録で10%オフになりますよ〜」
この人、只者じゃない。
そう直感した。
そして意を決して私は告げた。
「裾を15ミリ詰めて、裾幅を20ミリ細く。膝上からテーパードでお願いします」
この繊細なオーダーが伝わるのか?
と思ったのも束の間、「ああ、それなら大丈夫ですね」と、
さらりと受け取る手つきに、職人としての風格がにじんでいた。
10日後、スーツは返ってきた。
パーフェクトだった。
「なんか違う」が、「これが良かったんだ」に変わる瞬間。
たった数ミリの調整が、着る者の気持ちまで整えてくれる。
スーツって、やっぱり不思議だ。
かの凄腕の女性に、心から感謝している。
581/1000 物は語らず、私たちに問う
2025/07/05
物は語らない。
そして、語れない。
だから私たちは、物を「思い通りにできる存在」だと信じている。
使うもよし、仕舞うもよし、処分するもよし。
何ひとつ、文句を言ってこないからだ。
けれど、そうやって“思い通り”にした結果、
押入れの奥で、棚の上で、物たちは静かに時を止めてしまう。
まだ使えるのに、使われない。
生かされず、ただ「取っておかれている」。
それは、死蔵された命に似ている気がする。
私は、物にだって“役割”や“願い”のようなものがあると感じている。
食器は食卓で、服は体に寄り添って、
家具や道具は日々の営みを支えるために、生まれてきた。
なのに、それを奪っておきながら、
「捨てるのはもったいない」と自分に言い訳して、閉じ込めているのではないか。
一方で、「我が子」はどうだろう。
語る。語りかけてくる。
そして、決して思い通りにはならない。
心配し、悩み、時に腹を立てながら、
それでも私たちは子を見守る。
なぜなら、その存在に「意思」があり、「未来」があると知っているから。
物には意思も未来もない、と思われがちだけれど、
実は私たちがそれをどう扱うかで、
その“命の行き先”を決めてしまっているのかもしれない。
だから私は、物にも少しだけ、子に向けるような慈しみの目を向けたいと思う。
ただ便利だから、役に立つからではなく、
“今、ここで生きているか?”と問いかけるような目で。
子どもを押し込めて育てることができないように、
物だって、閉じ込めておいてはその価値を発揮できない。
今日も、手に取る。
使ってみる。譲ってみる。
そして、ときには「ありがとう」と言って手放してみる。
物は語らないけれど、
私たちの手の中で、その沈黙が意味を持つときがある。
579/1000 まだ海開き前。でも海もカニも、もう始めていた
2025/07/03
車で庄内浜の海岸線を走っていた。
窓を開けると、潮の香りがふわっと鼻をくすぐる。
その瞬間、「ああ、夏が来るな」と思った。
海開きはまだ先のはずなのに、
浜辺の空気は、もうすっかり夏の準備ができていた。
監視本部の前では、スタッフの皆さんが監視台や資材を運んでいて、
その様子にはすでに、夏の高揚感と緊張感があった。
今年も始まる。庄内の夏が。
ふと視線を海に向けると、もう海に入っている人たちがいた。
高校生くらいのグループがTシャツのまま、波に飛び込んでいる。
まだ“正式には”開いていないけれど、この暑さじゃ入りたくもなる。
夏は、誰かが「スタート」と言う前から始まっている。
そして道路では、ちょっとしたサプライズがあった。
モクズガニが1匹、トコトコと横断中。
あまりの暑さに誘われて出てきたのか
と思ったが、実はこの時期、彼らは産卵のために海へ下りてくるらしい。
モクズガニは普段、淡水〜汽水域に生息しているけれど、
夏になると、こうして海岸線の道路を横断することがあるのだという。
生き物たちは、人間の都合とは関係なく、ちゃんと自分たちのリズムで夏を始めている。
もしかすると、「開くのを待っている」のは僕たち人間のほうなのかもしれない。
海も、波も、風も、カニさえも、もうとっくにスタンバイOKだ。
今年もこの庄内浜が、何かを洗い流し、何かを始めさせてくれる気がする。
そんな夏の入り口に、車窓から少しだけ立ち会った気がした。592/1000 夏にウールコートを探す理由
2025/07/01
外は30度を超える夏日。
蝉の声が響き始めたばかりの昼下がり、
アイスコーヒー片手にスマホをスクロールしている。
探しているのは、ウールのコートだ。
この時期に?と思われるかもしれないけれど、
実はこれ、僕にとっては毎年恒例の“夏の始まりの冬支度”。
ちょっと変わってるかもしれないけれど、理にかなっていると思っている。
まず、夏の立ち上がりって、まだ目立たないけれど、しれっとセール価格で、しれっと在庫も豊富。
しかも最近は、セール価格でも返品OKのショップが増えている。
気軽に取り寄せて、気に入らなければ戻せばいい。
そのくらいの気持ちで冬物に触れられるのは、今の買い物の面白さだ。
実際、昨年はこの方法でダウンジャケットをゲットしている。
10月を迎える頃にはすでにスタンバイ完了。
「あ、寒くなったな」と思った日には、もう着られる。
あの感覚は、けっこう気持ちいい。
今、気になっているのはオリーブカラーのウールコート。
カーキより落ち着いていて、土臭さのない、どこか品のある色。
着こなせたらかっこいいと思う。
だけど、妻からは無難なネイビーを勧められている。
「手持ちの服に合うし、長く着られるよ」
それはその通り。ネイビーには安心感がある。
だからまずは、オリーブを取り寄せてみることにした。
実際に袖を通してみて、「やっぱりこれはハードル高いな」と感じたら、
その時は素直にネイビーにしようと思っている。
好きなものを追いかけながら、現実との折り合いもつけていく。
服選びって、そういう小さな判断の連続なんだろうなと思う。
汗をかきながらスクロールしたこの一枚が、
秋の朝に袖を通したとき、
「この暑さも、悪くなかったな」と思わせてくれる
そんな買い物になるといい。-
 794/1000 吹雪の中「あじまん」で一つになる
当社一大プロジェクト工事2日目、関東と名古屋から来てくださった職人さんたちを迎えたのは、吹雪だった。庄内式の手
794/1000 吹雪の中「あじまん」で一つになる
当社一大プロジェクト工事2日目、関東と名古屋から来てくださった職人さんたちを迎えたのは、吹雪だった。庄内式の手
-
 796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
-
 798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
-
 800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
-
 802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か
802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か