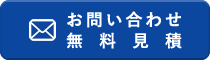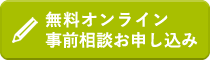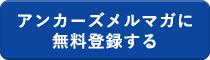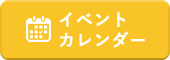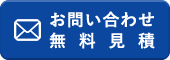- ホーム
- 毎日ブログ
毎日ブログ
590/1000 みんな居場所を求めてきた
2025/06/29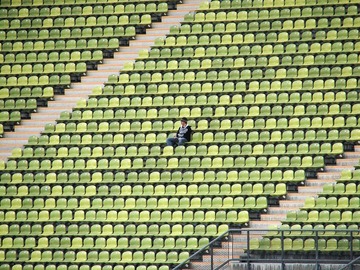
今日は、コロナの病み上がりということもあって、
朝からゆっくりめにウォーキング。
その流れで草刈りして、気になってたガレージの片付けまでやって、
身体を少しずつ“現世”に戻していた。
で、午後はと言えば──
『GUNDAM ジークアークス』全12話、6話から一気に観た。
いや〜、面白かった。
ファーストやZを観てきた身としては、ああいう“わかる人には刺さる”演出も多くて、じわじわ嬉しかったりする。
でも今回なにより印象的だったのは、「視点が変わったなあ」ってこと。
昔の自分なら、主人公にがっつり感情を乗せて観ていたはずなのに、
今はちょっと距離を置いて観てる。
なんなら、部長ポジションのシャリア・ブル目線の方がしっくりくる場面も多かった。
子どもの頃は、「俺を見ろ!」って叫ぶ主人公に、自分を重ねてた。
今はもう、ああいう真っすぐさに懐かしさすら感じてしまう。
今の若い世代が、ジークアークスの主人公たちに共感するのも分かる。
居場所がうまく見つからなかったり、空気を読みすぎてしんどかったり。
そういう中で、GUNDAMという“自分だけの居場所”に惹かれていく感覚は、昔も今も変わらないのかもしれない。
そして、自分が今そこに直接は共感できなくても、
「そうか、そういう時代なんだな」って少しだけ俯瞰で観られるようになったのは、
今のボクには居場所があるからなのかもな〜と思ったりした。
588/1000 岩ガキの季節に、父を想う
2025/06/27
庄内浜の初夏といえば、やっぱり岩ガキ。
「牡蠣といえば冬でしょ?」と思われるかもしれませんが、それは“真ガキ”の話。
庄内浜で旬を迎えるのは“岩ガキ”。春から夏にかけて冷たい雪解け水が流れ込むことで、身がぷっくりと太り、クリーミーで濃厚な味わいに育ちます。この時期にしか味わえない、まさに海の恵みです。
そんな岩ガキにまつわる、父の昔話をひとつ。
海辺の温泉街にあった父の実家は、決して裕福とは言えない家。けれど目の前には海がありました。海開き前のまだ冷たい磯に潜っては、牡蠣やワカメを採って空腹をしのいでいたそうです。
ある日、観光客がその様子を見て「その牡蠣、食べてみたい」と声をかけてきた。
父が焼いて差し出すと、その味に観光客は大喜び。
それを見た父少年、ピンときた。
「自分で食べるより、売った方がコスパがいいかもしれない」
そこからが父の真骨頂。
観光客が来そうな時間を狙って磯に潜り、網で牡蠣を焼く。
香ばしい香りが届くように工夫し、タイミングを見て、醤油をジュッと垂らす。
香りに誘われて足を止めた観光客に焼きたてを差し出せば……もう、完売。
もしかすると、父の“商いのセンス”は、この頃に芽生えたのかもしれません。
今、この季節に岩ガキを味わうと、父の話がふっと蘇ります。
磯の香りと、ジュッという醤油の音とともに。
でもね、本当に好きな人はこう言うんです。
「生で、レモン汁を搾ってどうぞ」と。
586/1000 浮かれないって、実は最高の幸せ
2025/06/25
何にも考えず、ひたすら寝る。
この数日、それしかしていない気がする。
3回目のコロナを経て、体も頭もシャットダウンモード。
ただ眠る。食べる。水を飲む。
そんな動物的な時間を過ごしていると、
逆に自分の中に、静かなスイッチが入るのがわかる。
「さて、次は何だ?」
そう思った瞬間から、自然と次のミッションに向かって
淡々と準備を始めている自分がいる。
この感覚、昔はなかった。
イベントが終われば打ち上げたくなって、
何かがうまくいけば、誰かに話したくなって、
落ち込めば、誰かに慰めてほしくなった。
でも今は違う。
次のステージへ。
ただそれだけを、静かに見つめている。
浮かれないで生きていられるってのが、
実は自分にとって、一番の幸せなのかもしれない。
余計なアップダウンがないから、
ちゃんと味わえるんです。
毎日の小さな手応えとか、
ゆっくり治っていく体の声とか、
ごはんがうまいとか、
それが一番だってことを。
584/1000 ビンゴとストラックアウトと、夏至の揺らぎ
2025/06/23
いつも、私の頭の中には“ビンゴ大会”のカードみたいなToDoリストがあって、
それを“ストラックアウト”の要領でシュバシュバとタスクを消していくのが日課です。
会議、資料、講話、連絡、現場確認、手配、ブログ……
ひとつずつ投げて当てて、消していくのが快感なんですね。
で、先週。
そのToDoの半分ぐらいが、一気にどさっと終わりまして。
気がつけば、リストはスッカスカ。
ビンゴ大会だったら「はいビンゴ〜!」って大喜びのはずなのに、
私の体はなぜかドッと重くなっていました。
“やること”があるうちは、
脳も体も“やるモード”になっているんだけど、
それが一気に終わると、急に電池が切れたみたいになるんですね。
それに加えて、日中の暑さと夜の涼しさ。
夏至とはいえ、こうも気温差があると体も迷子になりそうです。
——というわけで、今日はゆるめ運転で。
残ってるタスクも少しはあるけど、
それも“的外れ”にならないように、
今日はちょっと狙いを定め直す日にします。582/1000 「絶対に負けられない戦い」の、その先に
2025/06/21
「絶対に負けられない戦い」
そんな表現を、僕ら日本人はどうも好むらしい。
気づけば、自分の人生も、そんな“負けられない場面”に踊らされて来た気がする。
仕事、家族、地域の役割。
「ここは譲れない」「ここだけは…」と、自分に言い聞かせながら。
でも、ふと立ち止まって思う。
それは一体、誰との勝負だったのだろうか?
誰に勝つ必要があったのか。
勝ったところで、本当に得たかったものは手に入ったのか。
その答えが、実はずっと曖昧だった。
50歳を前にして、ようやく少しずつ見えてきた。
もう、誰かの尺度や物差しで自分の在り方を決めなくてもいい。
「自分はどうしたいのか」その問いを軸に選ぶようになった。
いや、もうすでに、選んでいる。
自分で選び、自分で納得し、自分でケツをまくる。
そんな生き方が、少しずつ自分の中に根を張っている。
勝ち負けじゃない。
どう生きて、どう終わるか。
腹をくくる先に、ようやく「自分らしさ」が見えてくる。
そんなことを
会社の経営というものを通して、僕は教えられた気がする。
社長業10年目の年。
ここまで来て、やっと本当の意味で「できる」と思えるようになった。
そして今、心から思う。
581/1000 覆面ピンチと、感度の話。
2025/06/19
ピンチはチャンス。
何度も耳にする言葉だけれど、
実際にチャンスへと変えられる人は、“感度”が高い人だと思います。
ただ、厄介なのは、
その“ピンチ”が、ピンチらしく姿を現してくれないこと。
先日も、ある出来事がありました。
表向きはうまくいっているように見えて、実際、周囲からも「よかったですね」と言われた。
でも、内心、何かひっかかっていたんです。
言葉にしづらい、ざわざわした違和感。
結果として、その“ひっかかり”は的中しました。
あとから振り返れば、あれは明らかに「覆面ピンチ」だったのです。
「順調」とか「ラッキー」とか、
そう思っていた時こそ、疑ってみる冷静さが必要なのかもしれません。
感度を研ぎ澄ますって、
実は、違和感をスルーしないこと。
チャンスを掴む以前に、
その覆面の下にある“ピンチの顔”を見抜けるかどうか。
日々の暮らしのなかで、
そんな目線を持っていたいなと思います。579/1000 犬山城の風と、初めての岐阜講話へ
2025/06/17
名古屋空港に降り立った瞬間、表示された気温は35℃。
蝉の声こそまだ聞こえませんでしたが、ジリジリと焼きつけるような日差しに、
「ああ、夏がすぐそこまで来ている」と肌で感じました。
その足で向かったのは、国宝・犬山城。
木曽川を望む高台に建つその姿は、まさに威風堂々。
天守閣に上がってみると、その高さに少し足がすくみました。
でも、それ以上に、風が気持ちよかった。
景色が開けていて、遠くまで見渡せて、「いま、ここにいる」という実感が、すとんと胸に落ちてきました。
城下町の散策もまた楽しく、
ふとすれ違った浴衣姿のカップルや、
地元のおじいちゃんの何気ない会話に、旅情を感じました。
そして明日は、人生で初めて岐阜県での講話に臨みます。
これまでさまざまな地域でお話させていただく機会をいただきましたが、
初めての土地というのは、やはり少しだけ胸が高鳴ります。
どんな出会いが待っているのか。
どんな言葉が、この場所で届くのか。
犬山の空の下、歴史の風に吹かれながら、そんなことを静かに思っています。577/1000 本日で、大役にピリオド
2025/06/15
娘のバレーボール部、三年生最後の大会である総体が終わりました。
これで部活動は引退。そして、私の保護者会長としての任も、ここで一区切りです。
昨年のソフトテニス部に続いて、二年連続の保護者会長。
部活が変われば、関わる人も内容も全く異なり、毎回が新しい挑戦でした。
バレー部特有の熱気、体育館での声援、親同士のつながり…。
学年を越えた温かいチームワークの中で、多くのことを経験させてもらいました。
そんな中、私が日々てんてこまいだったのを見ていた娘は、
「終わって、ゆっくりした?」と何度も聞いてきました。
まるで自分が迷惑をかけていたかのように、どこか責任を感じていたのかもしれません。
「大変だったけど、終わってしまうと不思議と全部いい思い出になるね。
テニス部の時よりも、自分がちょっと成長できた気がするよ」と私が言うと、
娘は「成長って…」と不思議そうな顔。
たしかに、大人になってからの“成長”って、子どもにはピンとこないのかもしれませんね。
でもこの歳になっても、役割や出会いを通じて、自分が少しずつ変わっていく感覚はあるものです。
誰かのために時間を使うというのは、
慌ただしい中にあっても、かけがえのない何かを残してくれるものですね。
ありがとう、バレーボール部。
そして娘よ、本当におつかれさま。575/1000 伸びしろセンサーが反応した日
2025/06/13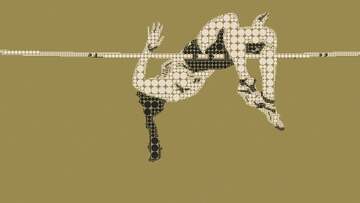
子どもの頃、自分の中に“ちょっと得意なこと”があるだけで、
なんとなく自信が持てた時期があった。
誰かに褒められるたびに、
「自分って、少しはすごいのかも」と思えた。
でも、あるとき気づく。
上には上がいる。
自分の「得意」は、案外通用しない。
その瞬間、自信が少しずつ崩れていく。
それ以来、本気を出すことが、少し怖くなった。
でも、たぶんそれ以上に怖かったのは、
自分の感情を表に出すことだったのだと思う。
悔しい、恥ずかしい、怖い。
そんな気持ちを見せたときに、
「弱いと思われるんじゃないか」と不安だった。
だから私は、感情を隠すために、
強がったり、笑ってごまかしたりする術を身につけていった。
ある日、信頼している人に言われたことがある。
「なんでそんなに平気そうな顔してるの? そんなに強くないくせに」
その言葉が、心に引っかかった。
たしかに私は、鎧のようなものをまとっていたのかもしれない。
大人になった今でも、何かに向き合おうとするとき、
背中の奥に、ゾワッとするような違和感が走る。
あの感覚は、長い間「不安」や「気持ち悪さ」として処理していたけれど、
最近になって、少し見方が変わった。
あれは、もしかしたら――
“伸びしろセンサー”なのかもしれない。
感情が動くとき、
自分にとって大事なものに近づいたとき、
そのセンサーがそっと知らせてくれている。
「ここを越えたら、変われるかもしれないよ」と。
だから最近は、センサーが反応したときこそ、
感情を押し殺すのではなく、少しずつ表に出してみようと思っている。
それでも迷うときは、
誰かに薦められたら、あえて乗ってみる。
ひとりじゃ進めないときほど、
差し出された言葉に乗っかることが、自分を広げるきっかけになることもあるから。
感情を出すのは、今でも少し怖い。
でも、怖いままでもいい。
その先にある“ちょっと新しい自分”に出会えたら、それで十分だと思っている。573/1000 ツバメ、再び 〜行き詰まりを壊すということ〜
2025/06/11
我が社のテラスに、またツバメが巣を作ろうとしています。
つい先日、第一陣が無事に巣立っていったばかり。
にもかかわらず、もう次の子育ての準備とは、彼らの切り替えの早さには毎年感心させられます。
ところが今回、巣作りの場所が“網戸の上”という、なかなか厄介な場所でした。
人間の出入りも多く、こちらとしては困りもの。
でも、ふと思ったんです。
「なぜ、すでに空になったあの巣を使わず、新しく作ろうとしているのか?」
これまで彼らは、ひとつの巣で年に2回、子育てをしていました。
それが今回は、前の巣を放置して、新たな場所に挑んでいる。
考えてみれば、ツバメは“巣を作ること”はできても、“巣を壊すこと”はできません。
自分で作ったものに満足できなくても、リセットが効かない。
だからこそ、不便でも新しい場所に挑まざるを得ない。そんな状況だったのかもしれません。
私は思い切って、空になった古い巣を撤去してみました。
すると翌日、なんとその場所に、彼らはまた巣を作りはじめたのです。
つまり、彼らはあの場所を“選ばなかった”のではなく、“選べなかった”。
壊すことができないから、選べなかったのです。
そこから私が学んだのは、
「行き詰まったら、ぶち壊す」という発想。
式年遷宮、20年ごとに神社を建て替える、あの古来からの習わしにも通じるものがあります。
何かを守りすぎて動けなくなることは、私たち人間にもあります。
でも壊してしまえば、また動き出せる。
繁栄の法則とは、実はそこにあるのかもしれません。
571/1000 水の音、風の匂い、そして倒れかけた家
2025/06/09
今日の一枚は、山形県鶴岡市の関川地区にて。
新潟県との県境にあるこの場所には、毎年梅雨前のこの時期に、なぜか仕事で訪れる機会があります。
ちょうど田植えを終えたばかりの水田。
そこを吹き抜ける風の涼しさと、川のせせらぎの音。
ああ、やっぱりここ、気持ちいいなぁと素直に思います。
この関川地区は、「しな織の里」としても知られています。
しな織とは、しなの木の樹皮の繊維を使った日本最古の織物のひとつ。
現在では新潟県の一部と、この関川にしか残っていない、貴重な技術文化です。
そんな風光明媚な土地ですが、今日ふと目についたのは、ところどころに見られる倒壊した空き家の姿でした。
放置されたまま朽ちてしまった家。
おそらく中には家財もそのままで、それが崩れた家の中から少し覗いてしまっている。
家が壊れると、モノも壊れる。
そして片付けも、安全な作業も、格段に難しくなる。
私たちは、こうした現場を何度も見てきました。
「せめて、家が壊れる前に、中のモノを引き受けてあげられていたら…」
そう思うことも少なくありません。
美しい風景の中に、少し切ない現実が混ざっている。
でもそれが今の地方のリアルであり、そこに私たちの仕事があるんだと思います。
まあ、できることを、できるうちにやるしかないか。
そんなことを思いながら、今日も走り出しました。569/1000 夢みたいな話
2025/06/07
まだ店内には入っていませんが、昨日オープンしたばかりの「無印良品 鶴岡」。
先月オープンした酒田店は大賑わいだったと聞いていたので、正直、鶴岡の方も混雑を心配していました。でも思ったほどの渋滞はなく、そこはちょっとホッとしています。
そもそも、鶴岡に「無印ができる」なんて、ちょっと夢みたいな話なんです(しかも会社から400m)。
これまで、買い物のついでに山形市や新潟に寄るしかなかったあの無印が、ついに“徒歩圏”に!
夢といえば──
つい先日、久しぶりにリアルな夢を見ました。
なんと、高校時代のサッカー部のたぶん何かの決勝戦で、私がハットトリックを決めるという、あり得ない展開。
48歳になってそんな夢を見ている自分に苦笑しつつも、それぐらい今回の“無印進出”は衝撃的だった、という話です(笑)。
まだ行っていないとはいえ、もうすでにあれこれ買うものをシミュレーション中。
あの収納用品とか、キッチン用品とか、ついでにカレーとか。
(ついでのついでに文房具も)
さて、鶴岡に新しい風が吹いた今。
モノの持ち方や暮らし方、ちょっと見直すいい機会になるかもしれませんね。567/1000 宇宙がぶつかると、ビジョンが生まれる
2025/06/05
長年ずっと、海ゴミのことが気になっていました。
仕事でもあり、趣味でもあり、いや──もはや“執念”かもしれません。
今日はそんなテーマで、横浜のメーカーさんとオンラインミーティング。
これが、ただの打ち合わせじゃなかったんです。
同じように熱い思いを持つ相手と話すと、
とにかく話が止まらない。
共通言語がいくつもあって、
ふたりの会話が次第に“対話”になって、
頭の中で何かが化学反応を起こす。
そして、降ってきた。
予想もしていなかった、とてつもないビジョンが。
これは──
人間と人間という“宇宙”がぶつかり合ったときにしか
生まれないものなんだと思いました。
ビートルズのジョンとポールがそうだったように。
全然違うふたりの中にある何かが、
重なり合ったときに、化け物みたいなエネルギーになる。
いま、そんな状態です。
これはもう、
とにかく横浜に行って、彼と直接話さなければ。
画面越しではもったいない。
リアルで“宇宙衝突”を起こしてきます。565/1000 果実が実れば、街も人も動き出す
2025/06/03
「佐藤錦が、ちょっと厳しいらしいね」
そんな話が、近頃あちこちから聞こえてきます。
さくらんぼ王国・山形県。
全国の約75%を生産しているとも言われるだけに、
この時期の空気には、どこかそわそわとした緊張感が漂います。
春先の天候不順や、開花時期の低温が影響したとか。
紅秀峰はどうにか大丈夫そうとのことですが、
佐藤錦に関しては、収穫量も味も、例年通りというわけにはいかないようです。
そんななか、ニュースではさくらんぼの盗難事件も報じられていました。
高級フルーツゆえの被害。
実をならせるまでの手間や時間を思うと、やるせない気持ちになります。
もうひとつ印象的だったのは、代行運転の方の話。
「さくらんぼが不作だと、夜の街の賑わいも減るんですよ」
毎年この時期、観光や取引で来た人たちが夜の街に流れていく。
飲み屋さんにとっても、さくらんぼは“稼ぎどき”なんだそうです。
さくらんぼって、ほんとに“季節を回す果物”なんだな、と改めて思いました。
そんな中
「さくらんぼ狩り行きた〜い」と、娘がぽつり。
珍しいことです。
どちらかといえばインドア派の娘が、果物狩りに興味を示すなんて。
なんとなくうれしくなって、「じゃあ行こうか」と即答した自分がいました。
毎年あるはずの季節の景色が、当たり前じゃないと知った今年。
家族で味わう一粒は、きっと少しだけ、特別に感じられるかもしれません。563/1000 薪は貸すな、の教え
2025/06/01
今日は、薪ストーブ用の薪作り第一弾。
山で切り出した木を、トラックに積んで家まで運びました。
汗だくにはなりますが、これはもう毎年の風物詩のようなものです。
この地域には、昔からこんな言葉が残っています。
「醤油や味噌は貸すが、薪は貸すな。」
はじめて聞いたときは、なんだかケチな話に聞こえました。
でも、薪というのは今日明日で準備できるものではありません。
切って、割って、乾燥させて…実際に使えるのは数年後です。
つまり薪は、“時間をかけて整える暮らし”の象徴なのです。
だからこそ、それぞれがきちんと用意しておくことが当たり前だった。
人に頼る前に、まず自分の冬を守る。それが“暮らしの礼儀”だったのでしょう。
今日積んだ薪が活躍するのはおそらく3年後の冬。
今、まだ見ぬ寒い朝を思い浮かべながら、汗をかく。
これは未来の自分と家族への、ちょっとした贈り物なのかもしれません。
備えるということ。
それは、誰かに頼らなくてもよいという、ささやかだけど誇らしい暮らしの形。
春の山仕事の先には、
ストーブの火に照らされた穏やかな時間が、きっと待っています。-
 794/1000 吹雪の中「あじまん」で一つになる
当社一大プロジェクト工事2日目、関東と名古屋から来てくださった職人さんたちを迎えたのは、吹雪だった。庄内式の手
794/1000 吹雪の中「あじまん」で一つになる
当社一大プロジェクト工事2日目、関東と名古屋から来てくださった職人さんたちを迎えたのは、吹雪だった。庄内式の手
-
 796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
-
 798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
-
 800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
-
 802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か
802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か