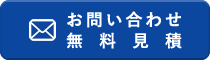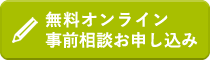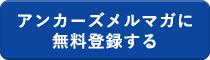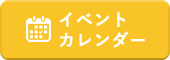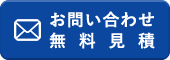- ホーム
- 毎日ブログ
毎日ブログ
713/1000 社長、集金に行く。
2025/10/31
今日は月末の金曜日ということで、何かと慌ただしい一日でした。
最近は振込やカード、ペイペイなど支払い方法も多様になり、集金に伺う機会も減りましたが、それでもいくつかのお客様のところへは直接お伺いしています。
行く先は実にさまざま。お寿司屋さん、ラーメン屋さん、喫茶店、イタリアン、定食屋、バー、居酒屋、花屋さん…。
「ゴミ」という切り口で、これほど多くの業種の方々と関わっていることに、改めて驚かされます。
「駅前が賑やかになってきたね」「観光客が戻ってきたよ」
そんな何気ない会話の中に、地域の景気や人の流れが見えてくる。
帳簿の数字だけでは分からない“リアルな温度”を感じる瞬間です。
そして改めて思うのです。
振込でもカードでもペイペイでも──お金を頂くというのは、決して当たり前のことではない。
それはお客様からの信頼であり、感謝の証。
この「ありがとう」を、対面で感じられることこそが、集金という仕事の原点なのかもしれません。
そして会社として、みんなで掴み取った仕事の集大成が、この集金。
現場で汗を流したスタッフ、事務で支えてくれた社員、そしてお客様。
そのすべてが一つにつながる瞬間が、まさにこの「ありがとうございます」の時間です。
やはり、社長こそ集金に出るべきだなと、改めて感じました。
711/1000 アンゾフのマトリクスが教えてくれた「決断の質」
2025/10/29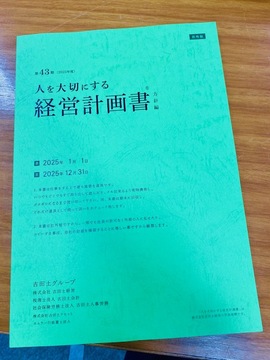
経営計画書作成合宿セミナー二日目。
講師は株式会社古田土経営(古田土会計グループ)。
経営計画書の作り方だけでなく、その“使い方”を徹底的に指導してくれる実践派。
今回の大きなテーマは「数字 × 戦略の質 × 行動の量」。
本日は戦略の質と行動の量にフォーカスした一日でした。
午前中は、弱者の戦い方として知られるランチェスター戦略をベースに、
「誰に」「何を」「どうやって」届けるのかを再定義。
改めてペルソナを設定し、なぜお客様が自社の商品を選ぶのかを掘り下げていきました。
やってみると、これまで“ニーズ”だと思っていたものが、実は自社の“シーズ(種)”であったり、
“お客様目線”のつもりが、実は自分たち都合の押し売りだったり。
気づきの多い時間となりました。
そして午後、一番心に残ったのが、アンゾフの成長マトリクスを使った「新規事業の決断」に関する講義でした。
既存市場 × 既存商品から始まり、新市場・新商品へと進む4つの方向性。
この図を、単なる“成長理論”ではなく、リスクと覚悟を見える化するツールとして解説されたのが非常に印象的でした。
講師の言葉が心に残ります。
「どこにリスクがあるかを見える化できれば、迷いではなく戦略になる。」
新市場 × 新商品、つまり“多角化”へ踏み出すとき、
人はつい夢や勢いで動きがちです。
しかし、アンゾフのマトリクスを冷静に当てはめると、
感情ではなく構造で判断できる。まさに意思決定の羅針盤です。
私はこれまで、どちらかと言えば直感で動くタイプでした。
けれど今日の学びで、直感に“理論の補助線”を引くことの大切さを実感しました。
「新しい挑戦をする」というのは、単に勇気を出すことではなく、
自社の立ち位置を見極め、進むべき方向を言語化すること。
その決断こそが、戦略の質を高める行為なのだと感じました。
数字 × 戦略の質 × 行動の量。
経営の結果をつくるこの方程式の中で、今日は「決断の質」を磨いた一日。
勢いではなく、確信をもって一歩を踏み出すための“思考の軸”を得られた、濃い二日目となりました。709/1000 二日酔いも、たまには悪くない
2025/10/27
先日の土曜日は、久しぶりに妻を連れて、ちょっと夜の街へ。
行き先は、当社でもごみ収集や厨房雑排水の清掃などでお世話になっている 和ビストロMARCO さん。
完全予約制、しかも看板は“表札レベル”という100%隠れ家的なお店です。普通なら気づかずに通り過ぎてしまうほどの控えめさ。そんなお店がずっと気になっていたのです。
ドアを開けると、予約で満席。カウンター越しに見える厨房では、丁寧に料理が仕上がっていきます。
舞茸の天ぷらとヤリイカのシュウマイで始まったコースは、どれも一皿一皿が印象的で、季節を感じる味わい。料理に誘われるように、日本酒が進みました。
最初は 白露垂酒(羽黒)、続いて 杉勇(遊佐)、そして 田酒(青森)。この田酒が、まぁ…旨い。
するすると喉を通り、気づけば何杯飲んだのか、自分でもわからないほど。お店の空気と妻の笑顔と日本酒の魔力。最高の夜でした。
…そして翌朝、しっかり二日酔い。
久しぶりの頭痛と、胃の奥に残るあの独特の感覚。歳を重ねると、“楽しい夜”のあとには、もれなく“静かな朝”がついてくるものです。冷たい水を一口、ふうと深呼吸。反省と幸せが同居する、不思議な時間。
「いや〜、よく飲んだね」と妻に笑われながら、少し重い頭を抱えつつ、そんな夜があるのも悪くないなと思った日曜日の朝なのでした。707/1000 組織の盛衰は、その書類からも見える
2025/10/25
今日のブログは、庄内お片づけ部の月に一度のミーティングについて。
先月開催された 無印良品 酒田 の「暮らしの保健室」内イベント「からだとくらしの広場」での整理収納イベントを振り返る反省会を行いました。
今回のイベントも、まさに“降って湧いたような”お話でしたが、そんな中でも部員一人ひとりの機動力とチームワークがしっかり発揮されたなと感じています。急な依頼であっても、「やる」と決まった瞬間から役割分担と準備が自然と始まる。この空気感は、ここまで積み重ねてきたお片づけ部ならではの強みです。
そこから話題は、各自の職場での「書類整理」の話へと発展しました。
やはりどこの現場でも共通しているのが、トップ層の“書類に対する無頓着さ”。「うちは昔からこうだから」「自分の代では捨てない」「移転のときにまとめてやる」という考えなんかが根強く、現場のスタッフの苦労がまったく伝わっていないケースが多いのです。
書類の整理って、誰もやりたがらない仕事なんですよね。
面倒だし、地味だし、達成感も目に見えにくい。しかも、やればやるほど今まで放置されてきた“ツケ”が浮き彫りになる。だからこそ、余計に誰も手をつけたがらない。
でも、誰かがやらなきゃ終わらない仕事でもあります。
結局のところ、整理を先送りすることで、日々の業務の非効率や情報のブラックボックス化が進むのです。
会社の衰退というのは、こういった小さな綻びから始まるのだと思います。
これは書類だけの話ではない、商品だって戦略だって「いつか」「そのうち」「今はその時期じゃない」と先送りにした結果、気づいたときには組織全体が鈍く、動かなくなっている。
トップが無関心、現場は疲弊。それでも現場の誰かが「ちょっとでもやってみる」ことから、会社の空気が変わることもあります。書類整理は、華やかさのない地味な仕事かもしれません。でも、だからこそ「会社を動かす力」を秘めている仕事でもあるのです。705/1000 業界の先を見据える対話
2025/10/23
昨日の 鳥海山 の初冠雪に続き、今朝は 月山 も白くお化粧をしていました。いよいよ冬がそこまで来ています。
昨日の社内ミーティングでも、今シーズンの除雪計画やタイヤ交換の話題がちらほらと。毎年のことながら、この話題が出ると「冬が来るな」と実感します。
そんな折、ある廃棄物の一元管理会社様から当社への会社確認がありました。こういったコンサル系の会社は世の中に数多くありますが、実際に現場まで足を運んでくださる企業はそう多くありません。その中でも、この会社の社長は毎年東京から自ら足を運んでくださる方。ありがたい限りです。
本来であれば当社へのヒアリングで終わるところですが、全国各地の処理業者を見て回っている方でもあるので、むしろこちらから質問攻め。業界の先進的な取り組みやこれからの方向性について、現場目線のリアルなお話を聞かせていただきました。規模は違えど、同じように会社を預かる立場として感じるものがあります。
視点はやはり「虫の眼・鳥の眼・魚の眼」。目の前の現実を感じながらも、10年後、20年後の未来と時流を見据える。そんな視点を共有しながら、互いの将来像を語り合う時間となりました。
歴史を振り返れば、超優秀と評された 徳川慶喜 も、将軍在任中は京都に留まり、江戸には一度も足を踏み入れなかったといいます。どれほど先を見通す力があっても、現場との接点がなければ、組織は動かない。
やはり「現場を歩く」ということは、いつの時代も変わらない大事なことなのです。
冬の足音とともに、業界の未来を静かに、しかし力強く見つめる一日でした。
703/1000 革ジャンと筋肉問題について
2025/10/21
急に空気が冷たくなり、日中も羽織ものが欲しくなる季節になりました。
ついこの前まで Tシャツ一枚や薄手のニットで過ごしていたのに、季節の歩みは早いものです。
この時期、庄内では「カメムシの量で雪の多さを占う」という、ちょっとした年中行事があります。
ところが今年は、その話題があまり聞こえてきません。
どうやら発生数が極端に少なく、いたとしても小さな個体で、すぐ弱ってしまうのだとか。
ということは、今シーズンの雪は少ないのか。それとも単なる迷信なのか——今年ははっきりしそうです。
そしてもうひとつ、秋の訪れを実感するのが、久しぶりに革ジャンに袖を通すとき。
今朝、ファスナーを引き上げようとしたら、胸のあたりでピタリと止まりました。
どうやら、パーソナルジムで鍛えた胸筋が知らぬ間に成長していたようです。
トレーナーに聞くと、この「革ジャンと筋肉問題」は、トレーニー界隈ではしばしば引き起こされる話題なのだとか。
革ジャンを取るか、筋肉を取るか——悩ましい秋です。701/1000 いい字とは「我」から解放されること
2025/10/19
今日のブログは、中々初段に上がれない習字の話。
頭で考えて書こうとすると、どうしても型にはめようとしてしまう。
筆に力が入り、線がこわばる。
けれど、本当に「書く」ということは、
水が流れるように、蔦が伸びるように、鳥が飛び立つように
ただ自然に筆先に身をゆだねる世界にあるのだろう。
でも、そこにたどり着くには「数」を書くしかない。
気づいては、また分からなくなり、そしてまた気づく。
そんな螺旋階段をぐるぐると登っていくような道のりだ。
「どうやったら自然に書けるのか」と考えている時点で、
もう頭で書いてしまっている。
子どもが上達するのは、考えないからだと聞いた。
一方、大人の習い事が難しいのは、
経験やプライドといった“邪魔者”が、自分の中に住みついているからだ。
自然に書くということは、
技術を覚えることだけではなく、
その“邪魔者”すなわち我と向き合い、解放されて行くことなのだ。700/1000 700回を超えると、見える世界があるらしい
2025/10/17
本日のブログは、このブログの連続更新が700日を迎えたという、ちょっとした節目のお話です。
このチャレンジを始めたのは2023年11月18日。
もともとは気まぐれに始めた日々のブログでしたが、整理収納アドバイザー仲間の三谷直子さんの「1,000日チャレンジ」に背中を押され、「よし、俺もやってみようか」と本格的に取り組むことになりました。
たまに「/1000って何ですか?」と聞かれるのですが、これは1,000回連続更新を目指しているうちの○○回目という意味です。
今日なら「700/1000」。なんだかゲームのレベルアップのようで、ちょっと気分が上がります。
ちなみに、このブログはお片づけのプロ集団アンカーズのHPに掲載しているものですが、実はもう一つ、母体である「環境管理センター」のHPにもブログがあります。
この二つを交互に更新してきた結果、二つ合わせて今日で700回を迎えました。
もしアンカーズのブログしかご存じなかった方は、ぜひこちらも覗いてみてください。
環境管理センターのブログはこちらhttps://www.kankyokanri.co.jp/contents_33.html
そして「1,000」という数字には、昔から特別な響きがあります。
たとえば、比叡山の千日回峰行のように、「千」を目指すチャレンジには一種の境地があるといわれています。
満願成就を果たした行者のインタビューを読むと、700回を超えたあたりから見える世界が変わるのだとか。
たかがブログ。されどブログ。
自分にもこれから、どんな景色が見えてくるのか。
少しワクワクしながら、また明日もキーボードに向かいます。698/1000 熊鈴とともに、不法投棄防止パトロール完了
2025/10/15
今日のブログは、不法投棄防止を呼びかける「秋のパトロール」が本日で終了したという話です。
このパトロールは、毎年春と秋に山形県、庄内地区の市町村、山形県警察、そして廃棄物処理業者が一緒になって行っているもの。人里離れた山林などに不法投棄がないか見回り、啓発を行っています。
今年のパトロールは、ちょっと様子が違いました。
それは「熊よけの鈴」を携帯しての巡回。ナラの実の不作が影響しているのか、今年の熊の目撃件数は昨年までとは比にならないほど。しかも不法投棄されやすい場所というのは、人の気配が少ない山林——まさに熊のテリトリーです。
最近では市街地でも出没しているとのことで、撃退スプレーが完売しているというニュースも耳にしました。みんな買うだけ買って、そのまま防災バッグの奥に眠らせるんでしょうね。けれど、いざ処分しようとすると「これ、どうやって捨てるんだっけ?」となる。スプレー缶は使い切って捨てるのがルール。でも撃退スプレーを“使い切る”なんて、現実的にちょっと怖い話です。
そして、今年もやっぱり不法投棄はあるのでした。
テレビのニュースでは流れないけれど、現場に行くと毎年同じような場所で見つかる。そこに置かれているのは、誰かの“いらなくなったもの”ではなく、誰かが“置いていった責任”です。
パトロールを終え、山の静けさの中で熊鈴の音を聞きながら、ふとそんなことを思いました。
「守る」というのは、不法投棄のないきれいな山も、そして人と熊との距離感も、両方なのかもしれません。606/1000 ちょっと嬉しい“お兄さん”
2025/10/13
数日前、白鳥が飛来しました。
夜にはストーブをつけたくなるくらい涼しく、秋の深まりを感じる今日この頃です。
本日は三連休の最終日。天気にも恵まれ、空が高い。
私はというと、田んぼで談笑中の白鳥たちを横目に、消臭作業へ行ってきました。
会社としてはお休みなのですが、この三連休を利用して帰省され、実家のお片付けやそれに伴う消臭作業のご依頼が何件かありました。当社で消臭作業ができるのは私だけということで出動です。
今日の現場はペット消臭。ご夫婦は私より少し若めくらいの方だったのですが、五十路間近の私のことを何度も「お兄さん」と呼んでくださったんです。
いや〜、最近そんなふうに呼ばれることなんてまずないので、ちょっと嬉しくなってしまいました(気をつかってくれたのだとは思いますが…笑)。
そして東京では、推し活で横浜に出かけた息子と友人が、下北沢の古着屋を物色中。
それを聞きつけた息子の姉(次女)が、小林家のグループLINEに「今から下北の駅に来い」とメッセージ。
それに対して息子の返信はひとこと——「ムリ」。
どんだけ塩対応なんだと父は思うのです。照れているのか、素っ気ないのか……。
いや、ちょっとは姉の顔を立てるとかあるでしょ。
うちのお兄ちゃんにも、もう少し愛想を学んでもらいたいところです。694/1000 92歳の終活から学んだこと
2025/10/11
昨日の夜、テレビのゴールデンタイム(この言葉、今はもう死語かもしれませんが)に「終活」をテーマにしたバラエティー番組が放送されていました。
十数年前には“重く語られる”ことの多かった終活が、今や笑いを交えながら全国放送で取り上げられる。そんな時代の移り変わりに、ふと驚きを覚えました。
そして本日は、昭和8年生まれ、92歳の男性のお宅に伺い、家財整理と家事代行についてのヒアリングをしてきました。
地方では家事代行という言葉自体、まだまだ馴染みが薄いようです。男性によれば、利用しているのは一部の医師や保険業の方ぐらいで、高齢者の利用はほとんどないとのことでした。
奥様を亡くされて一年。
「これからの人生と真正面から向き合いたい」と、私に声をかけてくださいました。
実は奥様がご存命の頃にも家財整理の件でご相談いただいたことがあり、その延長線上で今回は生活環境の改善を目的とした定期訪問のご依頼です。
印象的だったのは、この男性が紹介してくださった一冊の本。
介護未満の父に起きたこと(著:ジェーン・スー)。
この本から学び、ご自身のこれからの暮らしについて
①できること
②できないこと
③危ういこと
④頼みたいこと
を丁寧に分類し、「頼みたいこと」を明確にして、私たちにご相談くださいました。
現在、当社では家事代行に関しては外部の方をご紹介する形をとっております。
今後もこうしたご相談に対し、それぞれの暮らしに合った形で伴走できるよう取り組んでいきたいと思います。
「自分の未来の暮らしを、自分の言葉で整理する」。
その姿勢に、強さと静かな覚悟を感じました。693/1000 末の娘と大地讃頌
2025/10/09
我が家の末の娘は、保育園の頃からピアノを習っています。気が向いたときはふらりとピアノに向かい、好きな曲を弾いている姿はちょっとした日常の風景。
この時期は合唱コンクールに向けて、課題曲の伴奏を練習していることが多いのですが、今年はちょっと様子が違います。
実は今年、初めて伴奏者の予選で落選したのです。
これまでは当たり前のようにピアノ伴奏の座を勝ち取ってきた娘。負けず嫌いの性格をよく知る父としては、きっと心の奥では悔しいはずだと思っているのですが、表情はいたって冷静。
「別に〜」とだけ言って、ピアノの前に座り、弾いているのは――あの名曲、「大地讃頌」。
卒業式のクライマックスで卒業生が歌うこの曲を、今から練習しているということは……
リベンジを狙っているのか。
ピアノの先生の計らいなのか。
はたまた、ただの趣味なのか。
真意はわかりませんが、現時点でなかなかの完成度です。
娘なりの静かな闘志を、指先から感じる父なのでした。
卒業式の伴奏の席、さてどうなることやら。注目です。それにしても大地讃頌って盛り上がるね!
691/1000 ややこしくしているのは、いつも私
2025/10/07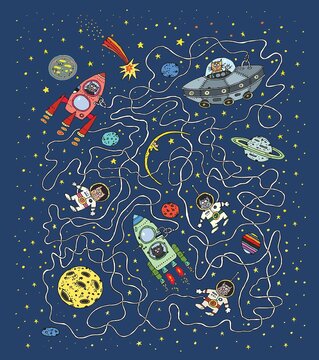
人間って、いつもいろんなことを考えていますよね。
「こんなこと言ったらどう思われるかな」とか、「失敗したら恥ずかしいな」とか。
頭の中でぐるぐる考えているうちに、前へ進めなくなってしまうこと、誰にでもあります。
でも、これって実は『お片づけ』にも同じことが言えるんです。
「これは〇〇さんから頂いた物だし」「高かったし」「思い出もあるし」「いつか使えるかも」
そうやって考えれば考えるほど、手が止まってしまう。
けれど、よくよく見つめてみると、状況をややこしくしているのは、他の誰でもなく自分なんですよね。
思い出も大切。でもそれに縛られすぎると、心まで動けなくなってしまう。
物の整理も、人間関係も、仕事のプロジェクトも、みんな同じ。
自分の“解釈”を事実にブレンドして、勝手に複雑にしてしまうんです。
だからこそ大事なのは、まず「事実」と「思い込み」をちゃんと分けてみること。
そして、「自分はどこへ向かいたいのか」というゴールを明るく描くこと。
そのうえで、そこへ進むための“最高のアクション”を選び取る。
言いにくいことほど、明るく爽やかに。
重く考えすぎず、軽やかに動いていけば、きっと心の風通しもよくなるはずです。
俺も、頑張ろっと!。689/1000 私、何にでもなれるって思っている。
2025/10/05
高校時代から、コロナ禍であったにも関わらず、どうしてもブライダルの仕事に就きたいと、専門学校に通うこと2年。
念願叶って、東京・青山のブライダルサロンにドレスコーディネーターとして就職した娘。
そんなピンポイントの仕事あるんだと驚いておりましたが、芸能人なんかも来るとかで、華やかな世界に足を踏み入れた彼女も、2年で転職。
今度の職場はアパレル関係の会社で、新人はまずフロアスタッフからということで、配属先はなんと横浜駅隣接の「ルミネ横浜」。
「専門学校、出なくてもよかったんじゃない?」なんて少し思ってはいますが、まあ娘の人生ですし、ということで新しい職場の“視察”へ。
ルミネというのは、田舎者の私にはまるで雑誌やSNSで見かける“ブランドのおせち料理”のようなビルで、やっぱり楽しいし、すんごい人。
どこを見てもキラキラしていて、働く人もお客さんも、みんなおしゃれ。
こんな華やかなところで娘が働いているんだと思うと、なんだかちょっと羨ましく感じました。
お昼休憩に一緒にランチをしながら近況を話し、「頑張ってやってるってみんなに言っておいて〜」と笑う娘。
その表情が少し大人びて見えて、心の中で“よくやってるな”とつぶやきました。
別れ際、ふと娘が言いました。
「私、何にでもなれるんだ!って思ってる」
あの頃、夢中で将来を語っていた高校生の顔が、一瞬だけ重なって見えました。
何になるのかなりたいのか、父も負けてられない。687/1000 倫理法人会創設45周年記念式典にて
2025/10/03
会場は〈飛天〉。フジテレビの音楽特番「FNS歌謡祭」などが開催される、まさに“テレビで見たあの場所”です。
初めて足を踏み入れた私は、その天井の高さとシャンデリアの輝きに圧倒されました。ステージの先に広がる空間は、画面越しよりはるかに大きく、そして荘厳。全国から1,500名を超える仲間が一堂に会し、45周年を祝う場としてふさわしい空気に満ちていました。
特別記念公演では、武蔵野大学教育学部教授の貝塚茂樹先生が登壇。「戦後80年と道徳・家族・国家」という壮大なテーマについて語られました。
冒頭で紹介された戦中派・吉田満の問いかけ――「もし豊かな自由と平和、それを支える繁栄と成長力が、自己の利益中心に費やされるならば、それは不幸である」という言葉が強く心に残ります。豊かさの裏に潜む“空洞化”への警鐘が、時代を越えて響いてきました。
続いて語られた「戦後80年の歴史」は、①敗戦と戦後改革、②高度経済成長と国民意識の変化、③冷戦後からAI時代までの3つに区分されました。共同体の解体と個人化、そして現代における「つながりの不明瞭化」。その流れを追っていくと、私たちが直面している課題が浮かび上がります。
そして特に興味深かったのが「ゴジラ」の話。
なぜゴジラは日本にだけ上陸するのか。なぜ皇居には決して手を出さず、破壊の途中でターンを繰り返すのか。そこには単なる怪獣映画を超えた「戦争へのアンチテーゼ」が込められているのだと先生は語られました。戦死者の亡霊を背負った存在としてのゴジラ。スクリーンの中の咆哮が、戦後日本の記憶と痛みを象徴していると考えると、子どもの頃に観た映画が全く違う意味を帯びて迫ってきます。
さらに心に残ったのは、次の言葉です。
「私のものさしで問うのではなく、私のものさしを問う」
「自分とは何か?ではなく、何が自分なのかを問う」
自分の価値観を振りかざすのではなく、その価値観自体を見直すこと。自分を一つの定義で語るのではなく、何が自分を形づくっているのかを問うこと。こうした新しい視点に触れることができたのは、この記念の場ならではの学びでした。
1,500名の熱気に包まれながら、私は改めて決意しました。
自分の中の「ものさし」を問い直し、日々の小さな選択の一つひとつに、その気づきを重ねて生きていこう。
なお、「飛天」のあるグランドプリンスホテル新高輪は、2026年度中に営業を終了する予定です。JR品川駅前の再開発計画の一環で、解体後は複合ビルが建設されるとのこと。
だからこそ、今日この場に立てたことは、まさに一期一会の体験であり、歴史の節目に立ち会えた貴重な時間だったと強く感じます。685/1000 携帯がつながらない時代の間接フリーキック
2025/10/01
最近ちょっと困っていることがあります。
それは「携帯電話から高齢者宅に電話をしても繋がらない」こと。
先日、私の携帯電話に「こちら山形県警捜査二課ですが…」と名乗る男性から電話がかかってきました。もちろん、次の言葉を聞く前に即切り。ドキッとしたのは事実ですが、詐欺電話に付き合うほど暇ではありません。
ただ一瞬、「捜査二課って『地面師たち』で辰さんがいた課だっけ?いや辰さんは警視庁の捜査二課か?」と、訳のわからない思考に迷い込んでしまいました。
それにしても、最近こうした正体不明の電話がやたら多いと聞きます。
だからでしょうか、本当に仕事で電話をしても出てもらえない。せめて留守電のメッセージから折り返していただければありがたいのですが、たいてい音信不通のまま。
結局どうするかというと、事務所の固定電話から掛け直すことになります。
携帯がダメなら固定から。これではまるで「間接フリーキック」。
相手から急ぎで!と指定されているのに、どうしてもワンクッション置かされる。
世の中の不安に備えるのは大事ですが、仕事の電話まで警戒されるのはちょっと切ない。
安心して電話ができる世の中、これからの課題かもしれませんね。-
 804/1000 予定のないドレスの話。未来の話ができるのが嬉しい
二泊三日の東京出張が終わり、雪の庄内に帰る。飛行場に止めた車の雪が心配だ。今回は中期経営計画を作成する合宿セミ
804/1000 予定のないドレスの話。未来の話ができるのが嬉しい
二泊三日の東京出張が終わり、雪の庄内に帰る。飛行場に止めた車の雪が心配だ。今回は中期経営計画を作成する合宿セミ
-
 806/1000 便利な後輩を卒業する
人を育てるということは、何なのだろう。仕事に限らず、これまでさまざまな立場で人と関わってきたが、振り返ると「自
806/1000 便利な後輩を卒業する
人を育てるということは、何なのだろう。仕事に限らず、これまでさまざまな立場で人と関わってきたが、振り返ると「自
-
 808/1000 節分の厄払い
今日は節分。季節の分かれ目で、かつて立春を一年の始まりとしていた頃の、いわば大晦日のような日だという。そんな日
808/1000 節分の厄払い
今日は節分。季節の分かれ目で、かつて立春を一年の始まりとしていた頃の、いわば大晦日のような日だという。そんな日
-
 810/1000 名前を呼ぶという贈り物
挨拶をされると、やっぱり嬉しい。それはきっと、誰にとっても同じだと思う。朝、すれ違いざまに「おはようございます
810/1000 名前を呼ぶという贈り物
挨拶をされると、やっぱり嬉しい。それはきっと、誰にとっても同じだと思う。朝、すれ違いざまに「おはようございます
-
 812/1000 身体がリアルに知っていたこと
ここ数ヶ月、歯が痛かった。神経は取ってある歯なので、歯そのものが原因ではないことは分かっていた。それでも、じん
812/1000 身体がリアルに知っていたこと
ここ数ヶ月、歯が痛かった。神経は取ってある歯なので、歯そのものが原因ではないことは分かっていた。それでも、じん