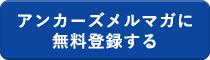727/1000 デジタルの向こう側にある、揺らぎの美しさ

今日、ラジオから久々にレイ・ハラカミの曲が流れてきた。
やっぱりいいなぁと思って聴いていると、
パーソナリティーが「この曲、実は古いデジタル楽器で作られているんです」とふと話した。
その一言で、音が急に立体的になった気がした。
完璧とはいえない昔のデジタル機材。
粗い波形や遅いレスポンス、経年の揺らぎ。
その“欠けた部分”が、逆にあたたかさをつくっているのだろう。
デジタルなのに人肌みたいな丸さがある不思議な音だ。
サブスクで音楽があふれるようになって、
曲の背景を知る機会はめっきり減った。
気に入ったら次、また次へと流れていく。
便利だけれど、奥のほうにある物語までは届かないことが多い。
そんなことを思っていたら、ふと90年代の頃を思い出した。
ケミカル・ブラザースが登場し、
打ち込みなのに妙に“生っぽい”ドラムに圧倒された時代だ。
メカニカルなはずのドラムが、なぜか人間の体温を持って聴こえる。
あれは、生ドラムのサンプルやMPCの揺れ、
アナログ卓の歪み、あえて整えないループ……
そうした“機材のクセ”そのものが音に残っていたからだ。
レイ・ハラカミの丸い電子音も、
ケミカルの荒々しいドラムも、
向き合っていたのは、生かデジタルかではなく、
もっとその先にある“揺らぎ”だったのかもしれない。
便利さがすべてを均一にしていく今、
こういう不均一な音に触れると、
なんだかホッとする。
そんな訳で、レイ ハラカミの
アナログ盤でも探してみるかと考えている。
関連エントリー
-
 812/1000 身体がリアルに知っていたこと
ここ数ヶ月、歯が痛かった。神経は取ってある歯なので、歯そのものが原因ではないことは分かっていた。それでも、じん
812/1000 身体がリアルに知っていたこと
ここ数ヶ月、歯が痛かった。神経は取ってある歯なので、歯そのものが原因ではないことは分かっていた。それでも、じん
-
 814/1000 これが都会の声量なの?
正月に仕事だった長女が、今になって帰省している。「何食べたい?」と聞くと、返ってきたのは「ココスー!」。都内に
814/1000 これが都会の声量なの?
正月に仕事だった長女が、今になって帰省している。「何食べたい?」と聞くと、返ってきたのは「ココスー!」。都内に
-
 816/1000 100℃の価値
今年はいろいろとチャレンジしたいと思っている。だからこそ、デフォルトでやるべきことを前倒しでどんどん進めている
816/1000 100℃の価値
今年はいろいろとチャレンジしたいと思っている。だからこそ、デフォルトでやるべきことを前倒しでどんどん進めている
-
 818/1000 それぞれの目線で見るオリンピック
熱戦が続くミラノ・コルティナダンペッツォオリンピック。我が家でも、自然と会話の中心になっている。妻は言う。「あ
818/1000 それぞれの目線で見るオリンピック
熱戦が続くミラノ・コルティナダンペッツォオリンピック。我が家でも、自然と会話の中心になっている。妻は言う。「あ
-
 820/1000 それぞれのバレンタイン
昨日はバレンタイン。末の娘がキッチンを占領している。毎年この時期は姉たちと取り合いだったが、今は独壇場。湯せん
820/1000 それぞれのバレンタイン
昨日はバレンタイン。末の娘がキッチンを占領している。毎年この時期は姉たちと取り合いだったが、今は独壇場。湯せん