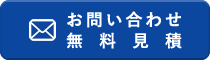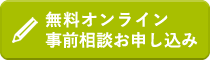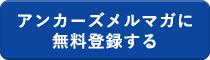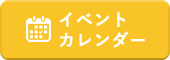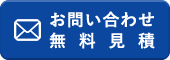- ホーム
- 毎日ブログ
毎日ブログ
561/1000 静かに変わる、夜の風景
2025/05/30
カッコウが涼しげに鳴いています。
初夏の鶴岡、空気が澄んでいて、外回りも気持ちのいい日でした。
月末ということで、今日は集金に。
件数は以前に比べて減ったものの、
馴染みのお客様と顔を合わせて言葉を交わせるのは、今となっては貴重な時間です。
飲食店に伺うことが多いのですが、
そこで耳にしたのは「最近、2次会に行く人が減ってね」という声。
その理由は、夜間の代行運転がつかまらないこと、
そしてタクシーの台数自体が減ってしまったことにあるそうです。
そういえば、ホテルから少し離れたエリアの店が静かで、
逆に近場のお店に人が集まっているという話もありました。
コロナが落ち着いても、街の風景は元に戻るわけじゃない。
代行、タクシー、そして人の流れ。
夜の鶴岡は、静かに、確かに変わっているようです。
それでも変わらず店を開けてくださる方がいて、
そこに灯る明かりが、どこか安心感をくれる。
小さな会話から、街の“今”を感じた一日でした。
559/1000 縁というのは、予測の外にある
2025/05/28
本日から開催の「NEW環境展(東京ビッグサイト)」に行ってきました。
業界人として、これはもう年中行事のようなもの。
20年ぐらい毎年参加していて、定点観測という意味でも欠かせないイベントです。
コロナの時期には規模がぐっと縮小されていて、正直少し寂しさもありました。
でもここ数年は、それ以前よりもむしろ活気がある。
出展者の熱量も、来場者の熱気も、肌で感じるほど戻ってきたと実感しています。
今年、特に印象的だったのは「金属リサイクル」のブースの多さと熱。
価格が上昇傾向にある影響もあってか、
これまで以上に注目を集めているように見えました。
鉄、銅、アルミ――それぞれの分野で技術と戦略が高度化してきているのを感じます。
今回は実は、ある“お目当て”があって会場を回っていたのですが、
一番の収穫は、その周辺にあった別のブースでした。
「これは…面白いぞ」と足を止めたのは、
事前情報ではノーマークだったある小規模な出展者の技術。
機械の音を聞きながら、その方とじっくり話をする中で、
図面の中にまだ描かれていなかったピースが、スッと埋まったような感覚がありました。
こういうのを、“縁”というのかもしれません。
狙って行くと、違うものに出会う。
計画と偶然、その両方を持ち帰ることができるのが、
この手の展示会の醍醐味ですね。557/1000 年に一度の“免許更新”
2025/05/26
本日は、環境管理センター 第48回 定期株主総会を滞りなく開催することができました。
ご出席いただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。
総会後の食事会では、年に一度、この機会にしかお会いできない株主の方々と、
ゆっくりお話しすることができました。
あらためて思えば、当社は私が生まれた年に創業された会社です。
今日お集まりいただいた株主の中には、その創業当時から支えてくださっている方々もいらっしゃいます。
同じ年数を一緒に歩んでくださっているという事実に、身の引き締まる思いがします。
話題の中で特に興味深かったのが、**運転免許の「高齢者講習」や「認知機能検査」**について。
「次の更新が近くて、最近はブルーベリーとかDHAとか、いろいろ飲んでるんだ」
「ルテインが20ミリ入ってるやつが効くっていうんだよ」
などなど、健康と向き合いながら運転を続けるための工夫が、あちこちで語られていました。
そこで私も、最近知人から聞いた90代の親御さんが新車を購入したという話を2件紹介すると、
「それはすごい、励みになるなあ」と、皆さん笑顔に。
株主総会というと堅い場のように思われがちですが、
こうして長く関わってくださっている方々の“生き方”や“気力”に触れられるのが、
この会の一番の醍醐味かもしれません。
年に一度、会社の現在地を確認する機会であると同時に、
私自身も背筋を伸ばして、これからの一歩を踏み出す時間になっています。
555/1000 2万トンを背負う背中
2025/05/24
令和7年度から、うちの会社では毎週土曜を“洗車デー”にしました。
もちろん、収集車は毎日きちんと洗っています。
それでもやっぱり、毎日の作業だけでは行き届かないところもある。
気づいてはいたけど、見て見ぬふりをしていた場所も。
そこで、週に一度、みんなで一斉に洗う時間をつくりました。
うちの収集車は、1日で10トン前後のゴミを集めています。
週4日運行、年間52週、10年使うとすれば――約2万トン。
家庭ゴミに換算すれば、ざっと2,000世帯の10年分にあたります。
それだけの暮らしの“あと”を、この1台が黙々と運んでくれている。
洗車デーでは、タイヤのすき間やドアの内側、ミラーの根元まで、
みんなで手を入れて、こすって、流して、ぴかぴかにしていきます。
「ここ、結構たまってるな」「意外と汚れてたね」
そんな会話が飛び交う土曜の午前。
不思議と、笑顔が多い時間でもあります。
街をきれいにする車を、きれいにする。
それは、自分たちの仕事へのささやかな敬意でもあり、
働く仲間へのちょっとしたねぎらいでもあります。
そして何より――
553/1000 RIMOWAとふつうの東京
2025/05/22
昨日から、中学生の娘が修学旅行で東京へ行った。
空港まで送って行った妻の話によれば、
集合場所ではクラスメイトの男子が興奮状態で喋りまくっていたらしい。
「テンションが上がりすぎてて、逆にこっちが疲れた」と苦笑していた。
一方の娘は、いたって静かだったそうだ。
どこか淡々としていて、でもその落ち着きの中に、
ちゃんと楽しみな気持ちがにじんでいたようだ。
思えば、一年前のこの時期、息子も東京へ行った。
彼は出発前、スマホが禁止というルールに備えて、
「どう撮るか」にこだわっていた。
ネットで調べて、2010年製のソニーのコンパクトデジカメを中古で購入。
写りの“味”がどうこう言っていて、らしいなと思った。
今回、娘はそのカメラをあっさり借りていった。
ただし、こだわったのはカメラを入れる袋の方だった。
「この柄はちょっと派手」「これじゃサイズが合わない」
何度も入れ替えて、自分なりの“ちょうどいい”を見つけていた。
兄は“中身”、妹は“持ち方”。
同じ道具でも、選ぶ視点がまるで違う。
そしてもうひとつ――RIMOWAのキャリーケース。
兄は、私のものを何の迷いもなく引っ張って行った。
娘は「これ、男っぽいよね」と渋い顔をしつつ、最終的には持っていくことにした。
このRIMOWAは、本当に壊れない。
どこにでも行くし、何度使ってもへこたれない。もう10年以上使っている。
そういえば以前、義母もこれを持って京都の寺めぐりに出かけたことがあった。
婆さんにRIMOWAは似合わない気もしたが、妙に楽しそうに転がしていた。
兄が使い、妹が使い、義母まで使った。
少しずつ、家族の旅の記憶がこのケースに溜まっていく。
今ごろ娘は、東京のどこを歩いているのだろう。
スマホは禁止だから、連絡はない。
でもそれでいい。
何を見て、どう感じて帰ってくるのか。
その答えが“ふつうだったよ”の中に、きっと隠れている。
551/1000 生まれた町で生きる
2025/05/20
今日で、庄内地区の不法投棄防止を呼びかける春の合同パトロールが終了した。
県・市町村・県警、そして私たち廃棄物処理業者がチームを組み、車で地域を巡回する。
この時期の庄内は、新緑が本当に美しい。
毎年のことだけれど、毎年ちがって見える。
今年は特に、光の具合がやさしくて、ただ車窓から景色を見ているだけで、心が少しほぐれていく感じがあった。
そして今朝、ふと感じたことがある。
海岸をランニングできること。
そして、生まれた町で今も暮らしていること。
それって実は、とても幸せなことなんじゃないかと。
波の音を聞きながら、誰にも邪魔されずに海沿いを走る時間。
この景色、この空気、この距離感。
いつもそこにあるものだけど、いつの間にか“当たり前”だと思っていた。
でも、本当はまったく当たり前なんかじゃない。
こうして走れる体があって、走れる場所があって、
見慣れた風景の中に自分が居るということ。
それは、何かに守られているような感覚すらある。
パトロールで見た景色も、朝のランニングで感じた空気も、
何も特別じゃないけれど、
「ありがたいな」と思えることが、今日の一番の収穫だった。549/1000 遠くまで行くために
2025/05/18
南は大阪、北は青森。
そして講師の先生は金沢から。
整理収納アドバイザーフォーラムin東北は、まさに「全国各地から、鶴岡へ」という言葉がぴったりのイベントになった。
無事に終了した今、これからは動画配信用の編集作業が始まる。
ここからが、もうひと山。
今回のフォーラムで表立ってはいないけれど、掲げていた大きなテーマは――「命を守る」。
整理収納という行為が、防災や災害時の安全にどうつながるか。
能登地震以前の取り組みと、これから地域で何ができるか。
それらを丁寧に見つめなおす時間だった。
人と人とのつながり、地域の力、そして“今を生きる”ということ。
それはすべて、命を守るという目的のもとにある。
決して特別な人だけがやることじゃなくて、
それぞれの暮らしの中にこそ、備えと気づきがある。
講師が仰った、心に残った言葉がある。
「早く行きたいなら一人で行け。遠くまで行きたいなら皆んなで行け」
アフリカの諺らしい。
これまで私は、一人で突っ走ってしまう場面も多かった。
でも今回のフォーラムは、まさに“皆んなで行く”という実感に満ちていた。
講師も、参加者も、関係者も、そして何より、運営スタッフのみんな。
あの人たちがいなければ、このフォーラムは成立しなかった。
走って、支えて、気を配って、笑って、考えて。
そのすべてが、「命を守る」というテーマに、静かに力を与えていたと思う。
この場を借りて、心からのありがとうを。
547/1000 無理だ〜の先にいる人たち
2025/05/17
今、でっかいプロジェクトに取り組んでいる。
でも、やってるのは私一人だ。
設計図作りって、やっぱり一人がいい。
もちろん関係者にはヒアリングしているけれど、あれこれ組み立てたり線を引いたりするのは、どうしても一人でこねくり回す時間になる。
だからなのか、ふとした瞬間に「もう無理だ〜」って、つい口から漏れる。
何度もあった、そんな瞬間。
だけど不思議と、そのたびに助けてくれる人が現れる。
自分で呼んだ覚えはないのに、ちゃんと絶妙なタイミングで。
なんだろう、これは。
最近は、「ああ、きっと守られてるんだな〜」と、ちょっと牧歌的な安心感すら湧いてきている。
昔の私なら、もっと気負っていたかもしれない。
全部自分の力で、歯を食いしばってやるべきだって。
でも今は、違う。
私は一人だけど、一人じゃない。
そんな矛盾が、今の私にはちょうどいい。
きっとこのプロジェクトはうまくいく。
だって、私は知っている。
「無理だ〜」と漏れた、その先で待ってる人たちがいることを。545/1000 迷った時の選び方
2025/05/15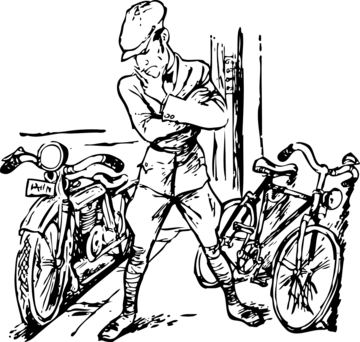
これまで私が迷ったとき、よりどころにしてきたのは「カタキ」の方だった。
“カタキ”とは、簡単に言えば**「難しい方」**。
楽な道より、骨の折れる道。
遠回りでも、手応えがありそうな方。
そういう道を選んでおけば、何となく「逃げてない気がした」からだ。
けれど実際は、その難しさに身を隠していたことも多かった。
「こっちの方が大変だから、きっと正しい」
そんなふうに思い込んで、でも本音では、本当に向き合うべきことからは逃げていた。
そのことに気づくたび、なんとも言えない罪悪感が残った。
難しい方を選んだ自分に酔っていたんじゃないか?
「正しい選択」という仮面で、どこか逃げていたんじゃないか?と。
そんなとき、『宇宙兄弟』というアニメに出会った。
その中で、主人公の六太が恩師から言われた言葉がある。
「迷ったときは、ワクワクする方を選べ」
私はこの言葉に、ハッとした。
自分が「難しい方」にばかり目を向けていたのは、
本当は“ワクワク”に自信が持てなかったからかもしれない。
心が動く方を選ぶことに、どこか後ろめたさを感じていたのかもしれない。
そして昨日、講演会で出会った言葉が、
そのふたつをすっと包み込んでくれた。
「迷ったら、両親が笑顔になる方を選びなさい」
この言葉には、計算も言い訳もいらなかった。
私の両親は今も健在だ。
どちらを選べば、あの人たちは笑ってくれるか。
その顔を思い浮かべれば、不思議と答えが出てくる。
“難しさ”や“ときめき”じゃなくて、
もっと深いところにある安心感。
それが、今の私にとっての道しるべなんだと思う。
これからも迷うことはあるだろう。
そのたびに、私は静かに自分に問いかける。
「両親が笑うのは、どっちだろう」と。
543/1000 草刈りとパールジャム
2025/05/13
夕方の小一時間、会社の敷地で今年一発目の草刈りをしました。
陽射しは穏やか、風はちょっとだけ涼しくて、やるなら今だなと。
草の勢いはすごくて、たんぽぽなんかは「おいおいどこまで広がるつもり?」ってくらいの勢い。
一部、完全に剛毛です。笑
草花には申し訳ないけれど、刈った後のスッキリした道端を眺めるとやっぱり気持ちいい。
それだけで、なぜか嫌なこともふっと軽くなるんですよね。
今日は草刈り中、久しぶりにパールジャムを流していました。
特に「Daughter」が妙にしっくりきて、無性に聴きたくなったんです。
1993年、あの曲を初めて聴いたのは高校2年生の頃。
親に対して反発していたような、でもまだどこか頼っていたような、そんな時期。
草を刈る単調なリズムと、エディ・ヴェダーの声が不思議に重なって、
心の奥にしまってた“あの頃の自分”とちょっとだけ再会した気がしました。
草刈りって、ただの作業だけど、どこか心の中まで整理されるようなところがあって。
パールジャムの音楽がそこに加わると、なんだか妙にしっくりくる。
もしかすると今、少し疼いてるのかもしれません。
50を前にして、あの頃のハングリーな気持ちが、また顔を出してきたのかも。
まあ、草刈りしながらそんなこと考えてる人もそういないとは思いますが、
こういう時間、わりと好きなんです。
541/1000 「50代からの資格取得」ランキングから思うこと
2025/05/11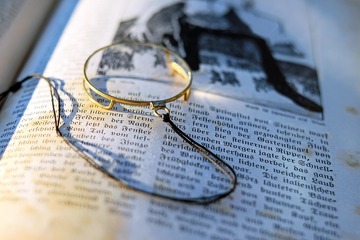
今朝の新聞で、「50代から取りたい資格ランキング」が紹介されていました。
1位:漢字検定
2位:習字・ペン字
3位:整理収納アドバイザー
そのランキングを見て、思わず「わかる、わかる」と頷いてしまいました。
48歳の私は、今まさに2位と3位を楽しんでいるところ。
習字を始めて約1年。今は二級を取得して、次のステップに向けて日々筆をとっています。
漢字のバランス、線の強弱、余白の取り方――
美しい文字というのは、単に整っているだけではなく、お互いの形が響き合い、引き立て合っていて、そこに書き手の感情や気持ちまで乗ってくる。
そんな「伝わる文字」を目指して、静かな時間に向き合うのは、なかなか豊かな時間です。
そして、もう一つの「整理収納アドバイザー」は、もはや趣味というより“仕事”の一部。
講師として、当社で月に1回、資格取得講座を開催しています。
とはいえ、モノを整えることは仕事でもあり、同時に人生を豊かにする“趣味”でもあると感じています。
整理収納は、形ある物体を整える技術だけれど、そこには「思いやり」や「おもてなし」、「モノを活かす」「自分を大切にする」といった、目に見えない価値が込められています。
習字もまた、線の美しさだけではなく、字に気持ちを宿す行為。
どちらも、「小さなことにこだわる」ことで気づける美しさや調和があって、
今の私には、それがとても心地よい。
そんなわけで、まんまと50代人気ランキングに乗っかっている私ですが(笑)、
日々をていねいに過ごしたい気持ち、わかる方も多いのではないでしょうか。
539/1000 手ざわりのある暮らしを、古道具から
2025/05/09
町家カフェ「古今coconn」への古道具搬入から、もうすぐ1ヶ月。
その間、たくさんの方に手に取っていただいた無塗装の無垢材でできた木箱。
多くの方が、このシンプルで温かみのある木箱を本棚として活用しているようです。
私たちが扱う古道具は、合板でもなく、最新の工場生産品でもない。
そして、匠の手による一品物の高級品とも違う。
それでも、等身大の暮らしにしっくりくる、そんなモノたちが揃っています。
例えば、木箱。
無塗装の木肌が手に触れたときに感じるあたたかさや、やわらかさ。
それは、どこか人の気配を感じさせるような、素朴で心地よい感触です。
こうした古道具には、完成されすぎていない“余白”があるからこそ、
使う人それぞれの暮らしに合わせて変化していく魅力があります。
完璧ではないけれど、だからこそ、毎日手を加えて育てていける。
その感じが、まさに「手ざわりのある暮らし」を感じさせてくれます。
古道具には、時を経て、誰かの手に渡り、少しずつ味わいが増していく力があります。
そんな道具たちが、町家の古い空間に息を吹き込み、
今という時代と古き良きものとのつながりを感じさせてくれるのです。
「古今coconn」での体験を通じて、
その温もりや暮らしに寄り添う手ざわりを感じていただきたいと思っています。
その場所で、過去と今が交差する瞬間を、ぜひ体感してみてください。
今、暮らしに必要なのは、完璧でないものかもしれません。
等身大のわたしにぴったりのもの、
無理なく、日々の中で馴染んでいくものが、古道具にはあります。537/1000 正しさがぶつかる前にできること
2025/05/07
最近、「正義」という言葉が気になるようになりました。
大げさなようでいて、日常の中にも「正義」はあると思うのです。
それはつまり、自分が信じている“正しさ”のこと。
私たちは誰もが、自分なりの正しさを持っています。
そして知らず知らずのうちに、「それが一番正しい」と思い込んでしまう。
でも、同じように相手にも、その人なりの正しさがある。
それがぶつかったとき、どうしても対立になってしまいます。
でも、「ああ、そういう考え方もあるのか」と思えたら、少しだけ気持ちに余裕が生まれる。対立の軸をほんの少しずらすだけで、心が軽くなることもあります。
鳥の目で俯瞰してみること。虫の目で相手の立場に立ってみること。
そんなふうに視点を変えることで、すっと肩の力が抜ける気がします。
でも、それができる時って、たいてい心に余裕があるときなんですよね。
最近、なんだか世の中がカサカサしているように感じます。
みんな余裕がなくて、自分のことで手一杯。
だからこそ、今こそ「整理」なのかもしれません。
モノを整理することは、頭や心を整えることにつながっています。
部屋が整うと、なんとなく気持ちも整ってくる。
そうして生まれた余白が、誰かの“正しさ”を受け入れるスペースになるのかもしれません。535/1000 GWは恒例の玄関を亀の子ダワシで磨き上げ
2025/05/05
今日は会社に行って、事務所まわりの大掃除。
まずは、毎年この時期恒例の、玄関テラコッタタイル掃除。
これまではずっとアルカリ洗剤を使っていたのですが、
今年は思い切って酸性洗剤に変更してみました。
業者さんに「テラコッタには酸性のほうが向いてますよ」と教えてもらって、
なるほどそれなら、と。
手にしたのは、毎度おなじみの亀の子ダワシ。
ごしごし、ひたすらごしごし……
気づけば2時間が経過。
仕上がりは上々。これまでよりも汚れ落ちが良く、タイルがワントーン明るくなった気がします。
ただし、手は荒れました。バッチリ。
このあと、ハンドクリームを三度塗りする羽目に。
続いて、つばめの巣があるテラスもお掃除。
こちらは糞でずいぶん汚れていたけれど、つばめの邪魔をしないよう慎重に。
気配を消しながらスピーディーに、ほうきをそっと動かす。
上からの視線(たぶんつばめ)を感じつつ、なるべく音を立てず、なるべく短時間で。
ちょっとした緊張感の中での掃除だったけれど、
なんとか、つばめたちの機嫌を損ねずに済んだ……はず。
会社の玄関は毎年こうして丁寧に磨くのに、
自宅の玄関はもう、いつ掃除したか思い出せないほど。
こういうところ、妻に見られたらきっと何か言われるだろうな……
そんな予感を抱きつつ、何も言われないうちに今日の掃除は終了。
手は荒れたけれど、玄関は気持ちよく仕上がりました。
さて、ゴールデンウィークも残すところあと二日。
ありがたいことに「ゴミ持ち込みできますか?」というお問い合わせもいただいていますが、
受付は5月7日(火)から再開となります。
今週は土曜日も受付しておりますので、ご都合に合わせてぜひご利用ください。
533/1000 鯉のぼりを上げる朝
2025/05/03
今年も、父と鯉のぼりのポールを立てた。
この行事は、もう15年近く続いている。
一人ではとても立てられない大きなポールで、二人の呼吸が合わないと倒れてしまう。
タイミングを合わせて、ぐっと持ち上げる。無言の共同作業だ。
うちの鯉のぼりは、父が私の息子のために買ってくれたものだ。
あのとき、父はどんな気持ちで選んだのだろう。
父はもともと、娘のほうを少し特別に可愛がる人で、
孫に対してもそれは変わらない。
だから、私の息子のために贈ってくれたことが、
少し不思議で、少し嬉しかった。
当時は、名前の入った鯉のぼりがまだ定番だった。
今見ると、空を泳ぐ鯉の腹にデカデカと息子の名前があって、ちょっと照れくさい。
でも、その“古さ”にこそ、時間の重みがある気がする。
ポールを立て終えたあと、風が吹くのを待ちながら鯉のぼりを見上げる。
父は何も言わないけれど、たぶんあの贈り物は、
孫へのもの以上に、「父になった私」への無言のエールだったのかもしれない。
毎年同じようで、少しずつ違う春の空。
今日もまた、変わらない風景の中に、静かな気持ちが流れていた。531/1000 地域を変えるのは、“足す”より“引く”かもしれない
2025/05/01
昨日の寒さが嘘のように、今日はじんわり汗ばむ暑さ。ここ鶴岡も、季節がぐっと前に進んだ気がします。
そんな中、行政の方々や工業団地の代表と、軽く打ち合わせの時間がありました。テーマは地域の課題。特に、若者の流出をどう防ぐかという話は、皆さんそれぞれに思いがあるようで、自然と議論も深まりました。
「こんなネットワークが必要なんじゃないか」 「若い人たちが集まれるような拠点があったら」 「もう少し情報発信を強化してはどうか」
いろんな「足す」アイディアが出てきて、それはそれでとても前向きだと思います。地域をよくしたいという気持ちが伝わってきて、聞いていてうれしくなりました。
でもその中で、僕はひそかにこう思っていました。
「何かを加える前に、いったん引いてみる必要があるんじゃないか」と。
私たちが日々お伝えしている整理収納アドバイザーの理論でも、まず最初にやるのは“整理”、つまり「不必要なモノを取り除く」ことです。そしてその前には、「どうしたいのか」というビジョンを描く。これがあるからこそ、“今”を見直すことができるんです。
この流れで、ふと昔の友人の言葉を思い出しました。
「ラーメンの味も確かめないで、いきなり胡椒を振るやつって、ちょっと野暮だよな」
彼はそう言って、まずは一口、真剣にスープを味わってから箸を進めるタイプでした。たしかに、“味見もせずに足す”のは、自分の感覚を信じてないことの裏返しかもしれない。地域も同じで、「足さなきゃ」と焦る前に、まず今の味を確かめてみる。その方がずっと豊かだし、誠実だと思うのです。
もちろん、答えなんて簡単には出ません。でもこうした対話の場そのものが、地域を整理していくための大切なプロセスなのだと感じました。
帰り道、暑さに背中を押されて、アイスコーヒーをひとつ。苦味の中に少しだけ甘さを感じながら、「やっぱり足すより引く、かもしれないな」と、考え続けていたのでした。
-
 794/1000 吹雪の中「あじまん」で一つになる
当社一大プロジェクト工事2日目、関東と名古屋から来てくださった職人さんたちを迎えたのは、吹雪だった。庄内式の手
794/1000 吹雪の中「あじまん」で一つになる
当社一大プロジェクト工事2日目、関東と名古屋から来てくださった職人さんたちを迎えたのは、吹雪だった。庄内式の手
-
 796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
-
 798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
-
 800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
-
 802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か
802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か