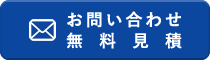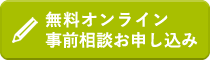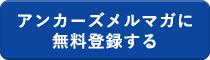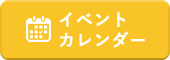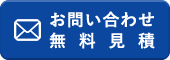- ホーム
- 毎日ブログ
毎日ブログ
529/1000 バーバーチェアに座る、それだけのことなんだけど
2025/04/29
2ヶ月に一度、顔剃りに床屋さんへ行っている。言っておくが、ただの顔剃りではない。90分。もはやコース料理並みの贅沢時間だ。最初の頃は「そんなに時間かかる!?」と思ったけれど、今ではこの90分がないと生きていけない身体になっている。完全に中毒。
椅子に座った瞬間、もう半分眠い。背もたれが倒れて、顔に蒸しタオルがのせられたら、はい終了。完全に宇宙へトリップである。天井の照明がぼんやり見えて「ああ、これが極楽ってやつか…」なんて思ってるうちに、いつの間にか顔がつるっつるになってる。
最近見た会員制の高級理髪店の写真が忘れられない。革張りの立派な椅子、静かな照明、木目の壁。完全に大人の秘密基地だ。もちろん行ったことはない。でも、妄想なら何度も行ってる。あの椅子——名前は「バーバーチェア」というらしい——あれに座るだけで、自分がちょっとデキる男になった気がするから不思議だ。
できればその部屋には、でっかいスピーカーも置きたい。アナログのレコードをかけて、針が落ちる音にうっとりするようなやつ。「音が空気を震わせる」ってこういうことか〜なんて言いながら、たぶんコーヒーか何かを飲む。でも気づけば、スピーカーより先に買ったのはレコードだけ、なんてこともありそうで怖い。あと、置く場所ね。スピーカーって本当に、でかい。
本当はあんな空間、自宅にもほしい。でも、あのアンティークな雰囲気って、どう頑張っても一朝一夕では出せないんだよなあ。うちのリビングにあの椅子とスピーカーだけ置いても、たぶん浮く。完全に浮く。まるで、おしゃれなスーツをパジャマの上に羽織ってるみたいな感じ。
527/1000 知らない人の結婚式に行ったら、まっこと面白かった件
2025/04/27
今日は、娘のバレーボール部の大会。
我がチームは昨日で敗退している。正直、今朝は重い足取りだった。「他人の結婚式」に出席しているような、心ここにあらずの、そんな一日になるはずだった。試合とは無関係な立場で、ただ時間だけが過ぎていくのだろうと。
ところが、会場に入った瞬間に、私の心は不思議と動き始めた。
白いロングTシャツに身を包み、颯爽とコートに現れたチーム。どのチームも地味な運動着に身を固めるなかで、そこだけがまるで光を放っているように見えた。練習の様子も独特だった。早々に練習を切り上げ、ゆったりとコートを広く使い、ペアでリズムを刻む。コーチも選手たちも、どこか余裕すら漂わせていた。
「このチーム、もしかして……」
そんな直感に突き動かされ、私はコーヒーを片手に、いつの間にかその陣地に溶け込んでいた。推理小説を鞄に忍ばせてきたけれど、読む暇なんてない。気付けば、視線も心も、彼女たちに釘付けだった。
試合が始まる。
出だしは苦しい。失点が続き、何度もタイムを取る。それでも、選手たちは決して下を向かない。点差は開く一方なのに、不思議と、希望の火が消えない。監督は冷静に試合を見つめ、スマホでストレス指数を確認して苦笑いする。その姿に、思わずこちらも肩の力が抜けた。
じわじわと点差は縮まるものの、結局、準々決勝敗退。
試合後、選手たちは黙って横断幕を外していた。その背中に、悔しさと、でもやり切ったという誇りがにじんでいた。胸がぎゅっと締めつけられる。
こんなにも胸を熱くする試合を、私は今日、目撃した。
朝感じた「つまらなさ」なんて、もうどこにもない。
むしろ、最高の日曜日。
私はまたきっと、バレーボールに魅了される日が来るだろう。
そう思えた一日だった。
525/1000 寝たいなら、スカッと起きろ!
2025/04/25
ここ2年ほど、どうも寝付きが悪い日が続いていました。特に「明日は早起きしなきゃ」と思えば思うほど、逆にプレッシャーになってしまって眠れない。あれこれ考えてしまい、時計を見ては焦るばかり。市販の睡眠改善薬なども試してみましたが、期待したほどの効果は得られませんでした。
そんなある日、ふと思いついたんです。「ゆっくり寝たいなら、二度寝をやめよう」と。
それまでは、寝付きが悪いから朝もスッキリ起きられず、布団の中でだらだらと過ごすことが多くなっていました。結果、生活リズムも乱れがちになり、夜になっても目が冴えてしまうという悪循環。
そこで、眠くてもまずは思い切ってスカッと起きることに決めました。二度寝したくなる気持ちはわかりますが、ぐっとこらえて一度で起きる。最初はなかなか大変でしたが、習慣になってくると、朝の時間が気持ちよく感じられるようになり、自然と夜も眠れるようになってきました。
早起きして体を動かしたり、朝日を浴びたりすると、心と体のリズムが整ってきます。すると不思議なことに、夜にはちょうどいい眠気が訪れるようになるのです。
結局、寝付きの悪さをなんとかしようと薬に頼ったり、寝る前の工夫をいろいろ試すよりも、朝の過ごし方を見直すほうが、私には効果的だったようです。
眠れない夜をどうにかしたい方にこそ、「まず朝しっかり起きる」を試してみてほしいと思います。
寝られないから朝起きられないのではなく、「朝起きないから夜眠れない」こともあるのだと、身をもって感じたこの2年間でした。525/1000 変わる所作、変わらぬ想い
2025/04/23
家財整理などでお客様のご自宅を訪ねると、ときおり妙齢の女性が、膝をついて丁寧にごあいさつくださることがあります。その所作は、どこか慎ましく、見ているこちらまで背筋が伸びるような気持ちになります。不思議と、男性や五十代くらいまでの方がそのようなふるまいをされることは、ほとんどありません。
ふと、実家の母の姿が重なります。昔から人の出入りには必ず膝をついて深く頭を下げていたものです。けれど先日、町内会費の集金に来られた方にその所作で応じたあと、膝を痛めてしまい、それ以来正座ができなくなってしまいました。年齢とともに、体の声に耳を傾ける必要が出てきます。
近年では、会食の場においても畳に座布団という設えは、どこかネガティブな印象を持たれるようになってきました。「足腰に不安がある」「立ち座りがつらい」といった声から、椅子とテーブルのスタイルを選ぶ会場が増えています。
こうした変化は日常生活にも表れていて、自動車を選ぶ際にも、乗り降りのしやすさから座面の高い車種が人気を集めています。ほんの少しの段差でも、体に負担を感じるようになる年代にとっては、日々の“移動”さえも見直しの対象になるのです。
時代が変われば、礼のかたちやふるまい方も変わってゆくもの。かつては当然とされていた美しい所作も、今の暮らしには少し窮屈に感じられることがあります。
523/1000 擬人化で見えてきた“暮らしの相棒”
2025/04/21
例にもれず、うちの犬もやってみた。結果はというと、ややぽってりとした中年女性に変身していた。目を閉じて舌をちょろっと出してる、あのいつもの寝顔そのまんま。なんというか、「ひと休み・ひと休み〜」って声が聞こえてきそうな感じだった。
面白くなってきたので、今度は自分の持ち物でも試してみた。毎日使っている鞄、長年愛用している腕時計、古びたスニーカー、そして20万キロ乗っている車。
こうして擬人化してみると、自然と「このモノに性格をつけるならどうだろう?」と考え始める。鞄は口うるさい相棒タイプ。中に何が入ってるか常に把握していて、「それ要る? ほんとに今日も持ってく?」と毎朝問いかけてきそうなイメージ。
腕時計は時間にうるさい冷静沈着な上司。無言でプレッシャーをかけてくるタイプ。スニーカーは気さくな幼なじみで、「今日はどこ行くの?」って顔して待ってる。車はもう完全に無口な親父。メンテナンスのタイミングになると、黙って調子を崩す感じ。
擬人化なんて、最初はただの遊びかと思っていたけれど、こうやって見えてくるのは、自分がそのモノにどれだけ情を抱いていたかということだ。長く使えば使うほど、「ああ、こいつと一緒に過ごしてきた時間って、やっぱり特別なんだな」と気づかされる。
AIが描き出すのは、モノの姿だけじゃない。自分自身の“見えない関係性”まで映し出してくれる。それがちょっと恥ずかしくもあり、でも不思議と温かい。
今は、家の中にあるモノ一つひとつを擬人化して、自分だけの「暮らしの登場人物図鑑」みたいなものを作ってみようかと考えている。意外と、人生の振り返りにもなるかもしれない。521/1000 鷹の選択とお花見と
2025/04/19
今年も会社の花見の季節がやってきました。
…と言っても、満開の桜の下でブルーシート広げておにぎりと缶ビール、というわけではなく、お店でしっかり料理とお酒を楽しむ、いわば“大人の室内花見”。そして、なぜか恒例になっているのが「社長のひとことタイム」。
堅苦しくせず、でもそれなりに考えさせるような話を…と、今年は「鷹の選択」というエピソードを持ち出してみました。
ご存じの方もいるかもしれませんが、これは長寿の鷹にまつわる寓話です。
鷹は40歳を過ぎたころ、くちばしが曲がり、爪が鈍くなり、羽も重くなって飛べなくなる。まさに“老いとの戦い”です。このまま死を待つか、それとも痛みと時間をかけて自分を生まれ変わらせるか。
鷹は山奥にこもり、岩にくちばしを打ちつけて壊し、新しいくちばしを待ちます。そしてそのくちばしで爪を抜き、羽をむしり、新しく生え変わるのを耐え抜く。そして、再び空へ飛び立つ――そんな話です。
まあ、実際の鷹がそこまで劇的な再生をするわけじゃないらしいんですが、これがなかなかいい寓話なんです。
今までのやり方が通用しなくなったとき、思い切って手放すこと、変わること。それは簡単じゃないし、痛みもあるけれど、その先にしか“次のステージ”はない。そういうことを、この話は教えてくれます。
そして実は、私たちの会社も今まさに、この鷹のように生き残りをかけて変わろうとしている真っ最中。
新しい挑戦をするときは、失敗もあれば、不安もあります。でも、変化を恐れずに前に進めば、きっとまた高く飛べるはず。
てなことで、今日はそんな真面目な話もしながら、みんなとお酒を楽しみたいと思います。
519/1000 見えないサインと古道具
2025/04/17
今日ラジオで、「植物は飢餓状態になると超音波を発する」と知った。乾いて水を欲しがるトマトが、目に見えない小さな音で助けを求めているという。人間には聞こえないけれど、動物や機械には感知できるらしい。
その話を聞いて、妙に心に残った。人も、誰かに気づいてほしくて、目に見えないサインを出していることがあるのではないか、と。無言のまま、何かを知らせるように。気づかれないそのサインは、まるで宙に浮いた音のように、静かに漂っている。
人は誰かとのつながりの中で、安心を得る。信じられる相手、落ち着ける場所、ことばのいらない時間。そういった「心地よく頼れるもの」があって、ようやく自分を保てる。けれど、つながりが持てないとき、人は代わりの何かにすがってしまう。スマホやお酒、食べもの、過剰な仕事や、誰かで埋めようとした孤独。それらはほんの一時、気をまぎらせてくれるだけで、ほんとうにほしいものとは少し違う。
そう考えているうちに、ふと身のまわりの「物」にも目が向いた。長く使っているマグカップの欠けた口元、やけに音の大きくなった冷蔵庫、なぜか目につくまま放っていた靴。もしかしたら、物たちもまた、何かを知らせようとしていたのかもしれない。ただの劣化や故障ではなく、「そろそろ休ませて」とか「ありがとう」といった、小さな声で。
517/1000 ツバメの巣と、古道具の居場所
2025/04/15
ツバメが、今年もやって来ました。
当社事務所の2階テラスにある、昨年の巣にそのまま戻ってきたようです。賑やかな鳴き声と小さな羽音とともに、何ごともなかったように巣に入り、子育ての準備を始める姿を見ていると、季節の巡りが確かに訪れたことを実感します。変わらぬ営みに、心がすっと整うような気がするのです。
今日、我々のパートナー富樫あい子さんが営む町家カフェ「古今cocon」が新たな節目を迎えました。
築150年の趣あるその町家で、これまでのカフェ営業に加え、日用雑貨と古道具の販売がスタートしたのです。
あい子さんは、この町家がある山王町で5年間温かくおもてなしをしてきた方。そんな彼女の手によって息を吹き返した町家に、私たちが家財整理の仕事を通して出会った古道具たちを、少しずつ卸しています。
家財整理とは、誰かの暮らしの記憶を丁寧に受け取り、未来へつなげていく仕事だと思っています。使い込まれた器、手になじんだ籠、時の流れが刻まれた木の小物。どれも、手放されてもなお、誰かの暮らしのなかで息をし続けたいと願っているように見えるのです。
そんな品々が、あい子さんの店の一角に静かに並び始めました。
ふらりと立ち寄ったお客さまが、「これ、母が使っていたのとそっくり」と手に取ってくださる姿を見かけると、過去と現在が、確かにつながっていることを感じます。
あのツバメのように、かつての巣をまた使うように。モノもまた、場所を変えて誰かの手で新たな時を刻んでいく。
私の仕事は、ただ整理することではなく、そうした循環をそっと手助けすることなのかもしれません。
日々の暮らしの中に、少しだけ立ち止まる時間が生まれる場所。
町家カフェの片隅で、そんな出会いを見届けていけたらと思っています。
古今さんのインスタはこちらから
https://www.instagram.com/cocon.tsuruoka?igsh=YXp6ZGNkNmZyN21x
515/1000 父として思う、部活動の意味
2025/04/13
末の娘が中学三年生になり、部活動の集大成である総体まで、あと2ヶ月を切った。
正直、父親としては部活動というものに複雑な感情がある。自分が中学生だった頃は、部活なんて理不尽のかたまりだった。怒鳴られたり、意味のわからない上下関係に従ったり、それが“当たり前”の空気だった。それでもやめるとか文句を言うなんてことはなく、ただ我慢してやりすごしていた。
でも、大人になって、そして今、親として娘の姿を見ていると、ふと思う。あの我慢に、本当に意味はあったのか? 耐えることでしか得られないものって、そんなに大切なんだろうか?私自身の人生に役立っているか?
それは「本人のためだ」とよく言われるけれど、それって一体、誰の“ため”?
それでも娘は、続けている。不満を口にする日もある。納得いかないことをぽつりと話す日もある。でも、やめたいとは言わない。その姿を見ていると、ただ流されているわけでもなく、自分なりに考え、折り合いをつけながら向き合っているのが伝わってくる。
最近では、何かに対する反応の仕方が少し変わった。言葉にせずとも、「まあ、いろいろあるけど私はやるよ」とでも言いたげな顔をすることがある。きっと、自分なりのやり方で、この部活との関わり方を見つけているのだろう。
あと2ヶ月。結果がどうなるかは正直分からない。でも終わったあとに、娘が「やってよかった」と思えるかどうか――それだけが、今の自分には一番大事な気がしている。
つい口を出したくなるときもある。でも、最後まで自分のやり方でやり切ってほしい。その背中を、静かに見ていようと思う。
513/1000 気づかないうちに出る自分の顔
2025/04/11
今日、お客さんのところに顔を出したら、「疲れてるね」と言われた。
特に何を話したわけでもなく、ただ「こんにちは」と挨拶しただけだったと思う。でも、そのひと言が返ってきたってことは、何か出てたんだろうなぁと思う。
自分では普通のつもりだった。特別忙しいわけでもないし、寝不足でもない。だけど、ふとした顔や雰囲気に、知らないうちに“今の自分”って出るんだなと、ちょっと思った。(ただちょっと新年度だから気負いみたいなものは存分にあったりもする。)
そんなに深刻な話じゃないけど、最近はときどき「自分の印象」を気にするようになった。誰かのためっていうより、自分の気持ちを少し上向きにするために。
たとえば、いつもより明るめのシャツを着てみるとか、季節の香りを選んでみるとか。髪にちょっと手をかけたり、靴をピカッと磨いたりするだけでも、気分が変わる。
そういう小さなことで、自分の中の「疲れたモード」を切り替えられる気がする。
周りにどう見られるかも大事だけど、何より、自分がちょっとご機嫌でいられるかどうか。
今日の「疲れてるね」は、そんなことを思い出すきっかけになった気がする。511/1000桜を追って、伊勢へ
2025/04/09
本日は仕事で名古屋に来ています。事情があって、山形から車でおよそ700kmの道のりを走ってきました。さすがに少し疲れましたが、桜前線を追いかけるような旅でもあり、道中は季節のうつろいを存分に感じる時間となりました。出発地の山形は本日が開花日。新潟・柏崎あたりはちょうど満開で、それより南では標高の高い場所をのぞき、葉桜が目立ちはじめていました。名古屋の桜はまだ見頃のようで、こうして移ろいのグラデーションを目で追える旅は、なんとも贅沢だったなと感じています。
そして明日は、少し早起きして伊勢神宮まで足を延ばす予定です。前回訪れたのは、私が12歳のとき。あのときはただ広くて大きい場所、という印象しかありませんでしたが、今年48歳、年男となった今、あらためてあの場所に立ってみたくなりました。人生の節目に再び訪れる伊勢の地。今回は外宮・内宮をゆっくり歩いて、春の風を肌に感じながら、自分の足で静かにお参りしたいと思っています。
509/1000 新年度、ちょっとだけ自分をアップデート
2025/04/07
今日は通勤途中、自転車に乗った新一年生らしき学生たちをたくさん見かけました。きっと今日から新学期なんでしょうね。新年も気持ちの区切りにはなりますが、4月の新年度もまた、何かを始めたくなるようなタイミングです。
私もこの春、新たに2つの目標を立てました。
1つ目は「午前7時までに出社すること」、そして2つ目は「筋トレを朝晩の2回行うこと」です。
以前、尊敬する経営者の先輩から「社長が朝7時までに出社している会社は、まず倒れないよ」と教えていただいたことがあり、それ以来、私もなるべく早く出社するよう心がけてきました。でも、いつの間にか7時20分くらいが“普通”になっていて…。この春、もう一度気を引き締めて「よし、7時出社を習慣にしよう!」と決意したんです。
…が、これがなかなか難しい。実際、目標を達成できたのは今のところ1回。あとは7時5分とか10分とか、あとちょっとなのに!という日が続いています。
その理由のひとつが、筋トレ。これまでは夜だけだったのですが、どうもそれでは物足りなくて、「朝もやってみよう!」と取り入れたら、まあ時間が足りないんです。でも、朝に体を動かすと、気持ちもシャキッとしていい感じなんですよね。
特に何か予定があるわけじゃないんですが、夏にはキュッと引き締まった体になって、ひとりでちょっとした達成感に浸れたらいいなぁ、なんて思っています。
507/1000 旅館を閉じたおかみさんとの最後の時間
2025/04/05
当社では、事業所から出る事業系ごみの収集を行っています。お取引先様は、法律事務所や高校、介護施設、工場、ラーメン店、居酒屋、旅館など、さまざまな業種にわたります。年度末になると、残念ながら閉店されるお店も多く、そのたびに寂しさを感じます。
先日お伺いしたのは、嫁いでから53年間、ずっとその旅館を守り続けてこられたおかみさんです。令和6年度でお店を閉じる決断をされたと伺い、その長い年月を共に過ごしてきたお店への愛情と、その決断に深い敬意を抱きました。
お客様のところへ足を運び、お話を伺うことは、私にとって本当に楽しく、また学びの多い貴重な時間です。それぞれの業種に根付いたお話や、お客様の思いを聞くことで、私たちのサービスもどんどん磨かれていくと感じています。こうした瞬間が、日々の仕事のやりがいとなり、心に残る大切な経験となっています。
しかし、やはりお客様がいなくなってしまうことは、その方との時間が一緒に消えていくようで、どうしても寂しさを感じます。おかみさんも、旅館を閉じた今でも、朝目が覚めると「お客さん泊まってたかな?」と思ってしまうそうです。「半分はゆっくりできるけど、半分は辞めたくない気持ちもある」「常連のお客さんには、まだ連絡できていないんだ〜」と、ぽつりと話してくれました。
これから商工会に行って申請など、やるべきことがたくさんあると話しながら、少し寂しそうに笑い、「あんたにやるんだから」と、茹でたサザエとワカメを手渡してくれました。
505/1000 粘り強さを持っているか
2025/04/03
そんな中、ある人が粘り強さを発揮して、物事を思い通りに進めているのを目の当たりにした。私なら「もう無理だ」と諦めてしまう場面でも、その人は決して引かない。その姿に感動し、自分にはまだ粘りが足りないのではないかと反省した。
503/1000 茹でガエルになってはいけない
2025/04/01
-
 794/1000 吹雪の中「あじまん」で一つになる
当社一大プロジェクト工事2日目、関東と名古屋から来てくださった職人さんたちを迎えたのは、吹雪だった。庄内式の手
794/1000 吹雪の中「あじまん」で一つになる
当社一大プロジェクト工事2日目、関東と名古屋から来てくださった職人さんたちを迎えたのは、吹雪だった。庄内式の手
-
 796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
-
 798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
-
 800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
-
 802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か
802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か