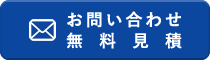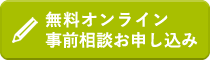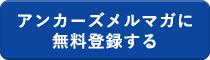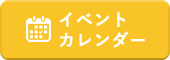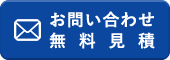- ホーム
- 毎日ブログ
毎日ブログ
810/1000 名前を呼ぶという贈り物
2026/02/05
挨拶をされると、やっぱり嬉しい。
それはきっと、誰にとっても同じだと思う。
朝、すれ違いざまに「おはようございます」と声をかけられるだけで、少しだけ心がほどける。
けれど今日、ふと気づいた。
挨拶の中でも、もう一段階嬉しい瞬間がある。
それは、名前を呼ばれて挨拶をされた時だ。
「おはようございます」ではなく、
「小林さん、おはようございます」と声をかけられる。
その一言に、少しだけ特別な温度が乗る。
自分をちゃんと認識してもらえている感覚。
ただの“そこにいる人”ではなく、“小林という一人”として見てもらえている感覚。
たったそれだけの違いなのに、不思議と心に残る。
今日、そんな挨拶を自然にしている人に出会った。
最初は、「自分だけ名前を呼んでもらえたのかな」と思って、少し嬉しくなった。
けれど様子を見ていると、その人は誰に対しても、当たり前のように名前を添えて声をかけていた。
それが実に自然だった。
わざとらしさもなく、頑張っている感じもない。
ただ、そこにいる人を大切に扱っているだけ、という雰囲気だった。
すごいな、と思った。
同時に、真似したいなとも思った。
仕事でも家庭でも、私たちはつい役割で人を見る。
担当者、作業員、社員、ドライバー。
もちろんそれも必要だが、その前に一人ひとりに名前がある。
名前を呼ぶという行為は、案外エネルギーがいる。
覚える努力もいるし、間違えないように気も遣う。
でも、そのひと手間が、人と人との距離をぐっと縮めるのかもしれない。
考えてみれば、自分の名前を丁寧に呼んでもらった記憶というのは、なぜか長く残る。
逆に、名前を呼ばずに済ませてきた場面も、きっと数えきれないほどある。
挨拶は毎日のこと。
だからこそ、ほんの少しだけ質を変える余地がある。
「おはようございます」に、そっと名前を添える。
それだけで、同じ言葉が少し違う意味を持ち始める気がする。
今日出会ったその人の姿を見ながら、
挨拶とは礼儀である前に、関係をつくる行為なのだと改めて感じた。
明日から、私も少しずつ試してみようと思う。
ぎこちなくてもいい。
名前を呼ぶところから、人との距離をもう一歩だけ近づけてみたい。
808/1000 節分の厄払い
2026/02/03
今日は節分。
季節の分かれ目で、かつて立春を一年の始まりとしていた頃の、いわば大晦日のような日だという。
そんな日に、私は車をぶつけられた。
駐車場に停めていた9年目のプリウスくん。
少し離れたところで、バックしてくる軽自動車が視界に入った。
「あ、近いな」
そう思った次の瞬間、派手な音とともにゴツん。
ぶつかる瞬間を、はっきり目撃してしまった。
手を振って制止すればよかったのかもしれない。
声を出していれば防げたのかもしれない。
後からなら、そんな考えはいくらでも浮かぶ。
向こうの車はバンパーがグシャグシャ。
一方、こちらは拍子抜けするほど、ほぼ無傷だった。
免許証を見せてもらうと、ゴールド免許のおばあちゃん。
長く無事故で運転してこられたのだろうと思うと、
怒りより先に、気の毒さが湧いてきた。
幸い、誰も怪我はしていない。
手続きは必要だが、それだけで十分だと思えた。
もろもろの厄が落ちて、誰かが持って行ってくれた。そんな気持ちが湧いてきた。
節分のごつんは幸先が良い。それで行こう。
806/1000 便利な後輩を卒業する
2026/02/01
人を育てるということは、何なのだろう。
仕事に限らず、これまでさまざまな立場で人と関わってきたが、振り返ると「自分より下が育っていない」という場面を何度も経験してきた。
私より上の世代は、次々と仕事を振ってくる。
私はそれを右から左へと処理してきた。
量をこなす中で、確かに力はついたと思う。
だが、ふと気がつく。
自分の下が育っていない。
下の世代は、私を当てにする。
「小林さんがいれば何とかなる」
その空気は、安心でもあり、同時に危うさでもある。
この構図が続けば、組織は静かに弱体化していく。
仕事は回っているように見えて、実は“人”が育っていないからだ。
頼まれることに応え続けるのは、気持ちがいい。
評価もされるし、自分の存在価値も感じられる。
けれどそれは、いつの間にか「便利な後輩」「都合のいい中間管理職」を引き受け続けることにもなる。
今、必要なのはもう一段階先の役割だと思う。
自分がやることを減らし、人に任せること。
失敗させ、考えさせ、時間をかけて待つこと。
人を育てるとは、
自分が楽になることでも、
相手を甘やかすことでもない。
組織の未来のために、
あえて自分が“不便になる”選択をすることなのかもしれない。
便利な後輩を卒業する。
それは、次の責任を引き受けるという決意でもある。
804/1000 予定のないドレスの話。未来の話ができるのが嬉しい
2026/01/30
二泊三日の東京出張が終わり、雪の庄内に帰る。飛行場に止めた車の雪が心配だ。
今回は中期経営計画を作成する合宿セミナーに参加していた。
合宿、と聞くと身構えてしまう。
山に籠もって数字と向き合い、頭から煙を出すような時間を想像していた。
けれど実際は、ずいぶんと穏やかな時間だった。
九割は個人ワークで、必要なときに専門家と壁打ちをする。
急かされることもなく、評価されることもない。
考えるための時間が、きちんと用意されていた。
かなり贅沢だし、驚くほど分かりやすい。
頭の中に散らばっていたものが、少しずつ整理され、
見えにくかった未来に輪郭が生まれてくる。
これからの会社、これからの仕事は、
きっとこういう形に近づいていくのだろう。
「仕事だからしょうがない」と割り切って進むのではなく、
立ち止まって考えること自体が、ちゃんと仕事になる世界。
そんな一日の終わり、上京している長女と飲みに行った。
話の中心は仕事のこと。
近況や悩みを聞きながら、
いつの間にか大人同士の会話になっていることに気づく。
ところが不思議なもので、
なぜか予定もないのに、
自分が着るウエディングドレスは何色がいいか、という話題で盛り上がった。
元ドレスコーディネーターの彼女は、
やはりドレスの話になると少し表情が変わる。
「こういうのはどうだろう」
私のチョイスに、
「そのブランド、人気だよ〜」と返ってきた。
少しだけ誇らしい。
何かが決まったわけではない。
未来が動いたわけでもない。
けれど、仕事のことを考える時間も、
予定のないドレスの話も、
どちらも「これから」を静かに見えやすくしてくれた気がする。
未来の話ができるというのは楽しいものだ。
802/1000 たまには一人がいいね
2026/01/28
東京出張1日目が終わった。
予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行かずにホテル。
せっかく東京に来たんだから、飲みにでも行けばいいのにと自分でも思うのだけれど、いつも全くそういう気分にならない。
多くの人は「もったいない」と言う。
たしかにそうなのかもしれないが、私はコンビニでお茶を買って、静かな部屋に戻る瞬間に、いちばんほっとしてしまう。
部屋に入り、夜景でも眺めようかとカーテンを開けると、隣のビルの壁だった。
思わず笑ってしまう。東京らしいと言えば東京らしい。絶景ではないが、がっかりするほどでもない。ただ、無機質な壁がこちらを静かに受け止めている。
若い頃は、知らない街に来ると意味もなく歩いた。外に出て、何かを取り込まないと損をする気がしていた。今は逆だ。一日分の言葉や判断で、身体も頭も満ちている。これ以上入れなくてもいい、とどこかで思っている。
ただ明日は、上京している長女と飲みに行く約束をしている。それを思うと、この静かな夜も、なんだかもう少しだけ賑やかだ。
誰の声も物音もしない、エアコンの音だけが響く部屋の中、家では味わえない、一人の静かな時間が、とっても心地いい。-
 794/1000 吹雪の中「あじまん」で一つになる
当社一大プロジェクト工事2日目、関東と名古屋から来てくださった職人さんたちを迎えたのは、吹雪だった。庄内式の手
794/1000 吹雪の中「あじまん」で一つになる
当社一大プロジェクト工事2日目、関東と名古屋から来てくださった職人さんたちを迎えたのは、吹雪だった。庄内式の手
-
 796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
-
 798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
-
 800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
-
 802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か
802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か