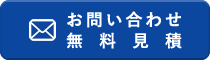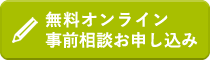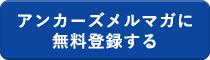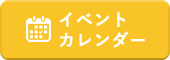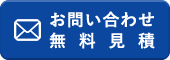- ホーム
- 毎日ブログ
毎日ブログ
800/1000 三十年越しの『BIG』
2026/01/26
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。
気づけば、三十年ぶりくらいになる。
当時は、「その頃脚光を浴びていたトム・ハンクスが出ている、昔の作品にBIGっていうのがあるらしい」という、そんな軽い情報だけで観た記憶がある。
とても印象に残る映画ではあったが、感動したという記憶はない。
この作品は、13歳の少年が、ある出来事をきっかけに、半年間だけ30歳の身体になってしまうファンタジーだ。
高校生だった私はもちろん子どもで、大人の世界への憧れや不安、そういった青さのただ中にいた。だからきっと私は、トム・ハンクス目線でこの映画を観ていたのだと思う。
それが三十年経って観ると、まず感じたのは、トム・ハンクスの演技の凄さだった。
まんま、13歳の少年が滲み出ている。声、動き、表情、間の取り方。そのすべてが「中身が少年」のままなのだ。
けれど今回、私がいちばん感情移入したのは、トムではなく、ヒロインだった。
トムはおもちゃ会社に就職し、そこで大人の女性と出会い、恋仲になる。
都会の大人社会で少し疲れた彼女が、トムと過ごすうちに、生きる喜びのようなものを取り戻していく。
ここから先はネタバレになる。
最後、すべての秘密が明かされ、彼女の目の前で、トムは13歳の少年に戻っていく。
恥ずかしそうに、気まずそうに、少し背中を丸めながら。
あの場面で彼女が向ける眼差しは、もう恋人を見るそれではなく、どこか母性に近いものだった。
そして別れのキスは、唇ではなく、おでこに。
切り替わる瞬間が、
この映画をコメディから“人生の話”に変えている。
今はズシンと胸を打たれるこのシーンを若い頃の私はきっと通り過ぎていた。
この映画の素晴らしさは、子供にも大人にも刺さる何かがあることだろう。
高一の息子に勧めて感想を聴きたいと思った。
798/1000 求められる自分と本当の自分
2026/01/24
久々の二連休初日。
それなのに、朝からなんだかそわそわしている。
仕事をしていないと落ち着かない。
もう体が、そういうリズムになってしまったらしい。
午前中は、凍えるコートでテニス観戦。
午後は床屋へ。
先月来たとき、「新年はパーマでイメチェンしましょう。テーマは“大人っぽく”で」と言われていた。
気づけば髪はくるっとしていて、色も少し明るい。
鏡を見ると、自分なのに少しだけ他人みたいで、少し照れくさい。
外側は変わったけれど、中身はたぶん変わっていない。
心の自分は、たぶんずっと16歳くらいのままだ。
でも現実では、求められるのは「大人の自分」だ。
落ち着いていて、ちゃんとしていて、頼られる側の自分。
その役をやりながら、内側では相変わらずの自分が動いている。
その二つの間で、毎日をやっている。
本当の大人のかっこよさって、何だろう。
弱さを隠す青さも悪くはないんだけれど、大人の悪あがきは見苦しい。やっぱり弱さを認めて笑い飛ばす潔さ。
たぶん私は、まだそこに向かっている途中だ。
だから今年は、「本当の大人」について考える一年になるのかもしれない。
求められる自分と、本当の自分。
その間で揺れながら、それでもごまかさずに立てる人。
そんな大人に、少しずつ近づいていけたらいいなと。
796/1000 寡黙な職人
2026/01/22
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。
詳細は、これから小出しにしていこうと思う。
この一年でいちばん寒い時期。
火の気のない工場での作業は、正直こたえただろうと思う。
吐く息は白く、金属は触るだけで体温を奪っていく。
指先の感覚が薄れていく中で、ボルトを締め、配線を通し、水平を取り続ける。
それはもう「仕事」という言葉では足りない、身体そのものの営みだ。
私はその昔、電気工事士として現場に出ていた。
だからなのか、今回工事に来てくれている電気屋さんのことが、どうしても気になってしまう。
盤の前に立つ姿勢。
腰袋の重さ。
工具を置く位置。
ブレーカーを落とす前の、ほんの一瞬の間。
言葉の端々に出てくる専門用語が、いちいち懐かしい。
そんな中に、ひとり、年配の職人さんの姿があった。
失礼とは思いながら、年齢を聞くと「七十六です」と静かに言う。
七十六。
正直、まったくそうは見えない。
背筋が伸びていて、動きに無駄がなく、若い職人たちと変わらない稼ぎっぷりだ。
脚立を押さえ、ケーブルをさばき、必要なときだけ口を開く。
「次は新潟の現場も頼みますね」
そう声をかけられても、彼は小さくうなずくだけ。
寡黙な職人。
その背中を見ながら、私は思った。
こういう人たちが、今の日本を支えているんだよな、と。
この人たちは、明日にはまたバラバラに、どこかの現場へ散っていく。
そう思ったとき、工事が終わった工場に、ふっと寂しさが漂った。
794/1000 吹雪の中「あじまん」で一つになる
2026/01/20
当社一大プロジェクト工事2日目、
関東と名古屋から来てくださった職人さんたちを迎えたのは、吹雪だった。
庄内式の手荒い歓迎である。
「それほど酷くならなくてよかったです」
そう言うと、職人さんが少し真顔で聞き返した。
「……これより酷い時、あるんですか?」
庄内の冬は「よくこんな所に住んでるね」とまで言わしめる凄まじさがある。
現場が少し落ち着いたところで、一服。
ストーブに寸胴をかけ、湯を沸かす。
そこに缶コーヒーを沈める。
横でクーラーボックスを開けると、湯気の立つ「あじまん」。
山形のソウルフード、大判焼きだ。
出来たてを買ってきて、冷めないように詰めてきた。
蓋を開けた瞬間、白い湯気と甘い匂いが立ち上る。
「おお……」
あちこちから小さなどよめきが起きる。
椅子はないので、ビールケースを並べて即席の腰掛け。
ストーブを囲んで、車座になる。
電気屋さん、機械屋さん、クレーン屋さん。
分野の違うプロフェッショナルが十数人。
手にしているのは、あじまんと、寸胴で温めた缶コーヒー。
誰かが言った。
「なんか、田舎の集会場みたいですね」
たしかにそうだと思った。
吹雪の外。
鉄の音の現場。
その真ん中に、ストーブと湯気と甘い匂い。
缶コーヒーは、ただの缶コーヒーじゃなかった。
寸胴で温めたそれは、指先から体の芯まで、まっすぐ効いてくる。
「あー……生き返る」
その一言で、今日ここに集まった理由の半分くらいは、もう十分だった気がする。
吹雪に当たり、あじまんをかじり、同じストーブを囲む。
工事二日目。
一体感がすごい。792/1000 それだけでいい日曜日
2026/01/18
冬の庄内は大抵、雨か雪か曇りの予報だ。
晴れマークを見ることは、ほとんどない。
「この時期、庄内の人はみんな鬱になる」
なんてブラックジョークが、わりと本気混じりで飛び交う。
それくらい、空は低く、陽は出ない。
最近、鬱っぽさとビタミンD不足には関係があるらしいと知った。
日光を浴びないと、身体の中でつくられるはずのものが、つくられない。
気分の問題だと思っていたものが、実は光の問題だったりもする。
だから今日は、晴れの日曜日。
寒鱈祭りが開かれていて、町はきっと賑わっている。
けれど我々は、人混みを避けて祭りには行かず、珈琲屋に入った。
窓際の席で、ただ陽を浴びていた。
ガラス越しの冬の光は弱い。
それでも、ちゃんと届く。
今日は、意識的に光をとりにいく日だと思った。
そのあと、生活が始まった。
妻の買い物の助手。
日用品の大量買い出し。
玄米三十キロを精米。
そして洗車が二台。
書き並べると、実に地味だ。
けれどこの土地では、こういう用事こそが「晴れの日の仕事」になる。
極め付けは、人生で初めて宝くじを買ったことだ。
妻が急に「買おう」と言った。
妻も初めてだという。
なんで、と聞くと、
「今日は当たりそうだから」
と、根拠のないことを、やけに静かに言った。
何に使うか、という話はしなかった。
家に帰ると、妻はその宝くじを神棚に上げた。
宝くじを買った、という楽しみを、存分に味わっているのだろう。
きっと、
陽の昇らない庄内の冬を楽しむための、
小さな仕掛けなのだと思う。
なんでもない日曜日
晴れて、動いて、珈琲を飲んで、宝くじを買った。
冬の庄内では、それだけで、いい一日になる。
-
 796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
-
 798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
-
 800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
-
 802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か
802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か
-
 804/1000 予定のないドレスの話。未来の話ができるのが嬉しい
二泊三日の東京出張が終わり、雪の庄内に帰る。飛行場に止めた車の雪が心配だ。今回は中期経営計画を作成する合宿セミ
804/1000 予定のないドレスの話。未来の話ができるのが嬉しい
二泊三日の東京出張が終わり、雪の庄内に帰る。飛行場に止めた車の雪が心配だ。今回は中期経営計画を作成する合宿セミ