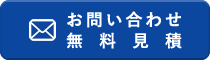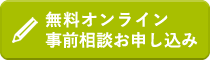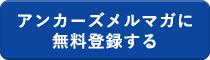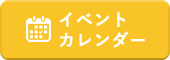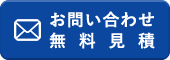水災害後の秋田市へ行く

2023年7月中旬、秋田県は豪雨災害に見舞われました。中でも内水氾濫と呼ばれる、排水機能の限界がもたらす都市型の浸水によって多くの住宅が床上・床下浸水の被害を受けました。
その後およそ一週間が経過し、断水の解消や災害ゴミの集積などが始まりましたので、現場ではどの様な事が起こっているのか実際現地に行きその状況を見て参りました。
私が訪れたのはニュースなどでも報道されていた災害ごみの仮置き場です。報道では置き場が許容を超える為自衛隊員が夜通し別の場所にトラックで移送しているということでした。行ってみると写真のように、家庭から排出される家財が堆く積み上げられ、環境省の方がドローンを飛ばしてその状況を確認する姿もありました。
現地で誘導する職員の方にお話を伺うと、受入は限界量に達しったため今日夕方でストップし、明日からは旧空港跡地で受け入れる事を教えてくれました。集積場では軽トラックから乗用車から、どこかの会社の小型ダンプなどで畳やらタイヤやら家電やら家具やら布団やらありとあらゆる家財が運び込まれ、その姿は皆汗だくで疲労しきっている様に見えました。
何人かにお話しを伺ったのですが、施設入居する夫を持つ80代の女性は、横浜から応援に来たと言う息子さんと集積場を訪れ、床上50cmほど浸水し、TVのインタビューを受けている間に家に入れないほど浸水し、泳いで命辛辛帰ったとおっしゃっておりました。
現在は住居の2階で生活しているがとても不便で、畳などをなんとか出して床を剥がして床下を乾燥させているとのことで、息子さんが消石灰をその床下の土に混ぜ乾燥を促進させるのだと行っておりました。30年以上住んでいるけれどこんなことは初めてだとその女性は仰り、火災保険の適用について伺うと、数年前の見直し時に保険の制度見直しがあって水害が特約になったのだそうで、その説明がなかったため特約を付けておらず、保険適用外ということでどうしたらいいものやらと不安げな表情でした。パート2に続く
関連エントリー
-
 752/1000 人に磨かれる、という話。
昔、「ダイヤモンドはダイヤモンドで磨かれる。人も人から磨かれるんだよ」そんな言葉を教えてもらったことがある。そ
752/1000 人に磨かれる、という話。
昔、「ダイヤモンドはダイヤモンドで磨かれる。人も人から磨かれるんだよ」そんな言葉を教えてもらったことがある。そ
-
 754/1000 「モノを本当に大切にする」とは
モノを本当に大切にするとはどういうことだろう。新品を傷つけないように扱うとか、高い物を大事に使うことだけではな
754/1000 「モノを本当に大切にする」とは
モノを本当に大切にするとはどういうことだろう。新品を傷つけないように扱うとか、高い物を大事に使うことだけではな
-
 756/1000 整理収納アドバイザーは魔法使いではない
整理収納アドバイザーとして、十数年活動してきた。整理の大切さについては、もう嫌というほど分かっている。それでも
756/1000 整理収納アドバイザーは魔法使いではない
整理収納アドバイザーとして、十数年活動してきた。整理の大切さについては、もう嫌というほど分かっている。それでも
-
 758/1000 今なら、あのコートを着られる気がしている
昨日は、久しぶりにリユースショップへ、モノを手放しに行ってきた。ジャケットが一着、ベストが一着、パンツが一着、
758/1000 今なら、あのコートを着られる気がしている
昨日は、久しぶりにリユースショップへ、モノを手放しに行ってきた。ジャケットが一着、ベストが一着、パンツが一着、
-
 760/1000 ストロングスタイルで向き合う、顧客データ
今、私は顧客データの整理という、ひとつの大きなプロジェクトに向かっている。正直に言えば、一円にもならない仕事だ
760/1000 ストロングスタイルで向き合う、顧客データ
今、私は顧客データの整理という、ひとつの大きなプロジェクトに向かっている。正直に言えば、一円にもならない仕事だ